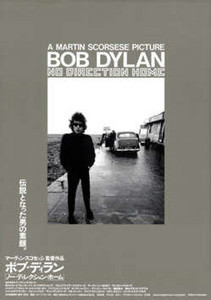注意:iTunes for mac/winか、Quick Timeで見て下さい。
今朝、雑誌が発行されたので、電話インタビューに対する回答内容を公開する。(公開にあたっては、先方の許可を得た。)
ツールを使うのは、学びを楽しくするためであり、その一つとしてポッドキャスティングを活用しているという意図がご理解頂ければ幸いである。(でも、雑誌記事では、記者が私に言わせたかったのは、ポッドキャストは安価に容易に情報発信させたかったようである。「百分の一、千分の一」という言葉は、向こうの言葉だった。)
録音できた音声は、私の声だけだったので、編集部側の質問を思い出して文字にしようと思ったが、物覚えの悪い私のアタマでは無理だった。そこで、相手の質問を文字化するのを最低限にして、むしろ私の回答の一部を文字化することに留めた。
文字をできるだけ少なくして、音声だけで聞かせる方がドキュメンタリー的でいいのだが、ここはエンターテインメント的な色彩を出すために文字を多くした。おかげで、音声だけだと軽いファイルが、結果的に重くなってしまったことは反省点である。これは今後の課題としたい。
なお、雑誌記事のタイトルが「東大、慶応などiPodでどこでも授業」とあるのは、精華大学との知名度の差である。専門店タイプで迫る必要がある。
以下、記事引用
パソコンやネットワークを使い教育を行う「eラーニング」に取り組んできた京都精華大学の筒井洋一教授は、「これまでのeラーニングは専用サーバーや太い回線を必要とするなど費用もかさんだ。発信側としてはポッドキャストなら百分の一、千分の一でできる利点があり、学生側にも時間や場所に制約を受けずに楽しみながら学べる利点がある」と普及を期待する。