遅ればせながらビデオで見ました。『パッチギ』という名前を聞くと、どうしても思い出してしまうことがある。ブログにまだ書いてなかったようだ。これを語らずしては映画にまで行かないので、しばらくご辛抱を。
昨年初めに封切りされたこの映画の評判を聞いた場所は、祇園のお茶屋さんだった。祇園のお茶屋といえば、舞妓さんや芸妓さんらに囲まれてさぞかし贅沢な遊びを満喫したと思われそうだが、私の用件は遊びではなく、謝りに行ったのだった。そう言うと、「筒井さん、遊びすぎが祟ったのね」と冷やかされそうだが、そういう優雅な生活とは縁遠い。
実は、大学の講義で学生が舞妓さんの仕事を撮影するという話が進展して、お茶屋さんも一度は承諾してくれた。しかし、間を取り持つ学生の説明がまずくて、先方が不審に思い、一気に破談になりそうだった。このままでは授業が継続できなくなると思って、私が謝りに行くことになった。それ以前にまずメールで当方の不手際をわびた。その上で、教師としては学生に授業を全うさせることが大事だと思うので、なんとか撮影の継続をお願いしたいと伝えた。相手への謝罪と私の教育に賭ける信念を伝えた力のこもった文章が書けたと思う。
このメールに反応したお茶屋のご亭主が電話してこられて、「学生からの細切れな連絡では一向にわからなかったですが、先生の説明を読んではじめて全容がわかりました。ところで、どうされますか? 女将にお会いになりますか? よければ、今晩遊びに来られますか?」という申し出に、出費は覚悟しても女将に会ってお詫びが言えるまたとない機会なので「是非参ります。ありがとうございます」と返事して出かけていった。
祇園の人に京都の手みやげは持って行けないので、大阪に行って買い、京都へすぐに折り返した。祇園の夜もまだ半ばの頃、気持ちを沈めてお茶屋のベルを鳴らすと、見習いさんがバーに連れて行ってくれた。女将は先客を接待していたので、一礼して端の席で待機していた。とにもかくにも、まず手みやげをお渡した。女将が時々来て、「もっと気楽にしてください」とか言われるけど、とてもそんな余裕はない。背筋を伸ばして、ただ気持ちを抑えるだけが精一杯だった。
しばらくして先客が帰ったところを見計らって、座布団を外して、畳に土下座をしながら、ひたすら謝った。「そんなことしてもらわなくてもかましません」と言ってもらったが、まだ気持ちは収まっていなかったようだ。メールで説明した内容を簡潔にかつ気持ちを込めて説明したところで、「おかわりいかがどすか?」と来る。「では、同じ物を頂きます」と答える。そのうちに、「うちの先生(ご亭主は学校の先生なのでそういう呼び名で呼んでおられる)はもう少ししたら帰ってきますので、それまでお待ち下さい」という話があった頃から少しずつ女将の機嫌が直ったのがわかってきた。
しばらくして、「学生さんが撮影される舞妓さんのお披露目会があります。破格の値段ですが、高級料亭の料理付きです。いかがですか?」と誘われた。確かにお茶屋遊びの相場ではなく、普通の料亭の夕食よりも安いかもしれない。「他の人も呼んでいいでしょうか。よければ二人で行きたいのですが」と尋ねると、「どうぞおいでください」と返答があった。こういう特別の催しに呼んでいただけるのは、きっと気持ちを収めてくれたのだと理解した。
(お披露目会ではご祝儀を持参するのが当たり前である。ポチ袋にお祝儀を包んでお渡ししたのだが、寝る前に中身を入れるのを忘れたことを思いついた。冷や汗が出た。翌朝お茶屋に伺ったが、祇園町の朝は遅いので誰も出てこない。そこで、その晩再度お茶屋さんに出かけてお祝儀を渡した。しかも金額はもちろん増額するのが常識というものだ。失敗が重なり、結局高くついたが、その店とは既に一見さんではなくなったのが唯一の自慢かも。すべて出してもらえるならば、喜んでお伴しますよ。)
1時間ほどして「先生」が戻ってこられた。そこで、まず座布団をはずして、土下座して心からお詫びした。女将が撮影には気が進まないのを、「教育目的」という点が教師の本性をくすぐったらしく、「先生」が間を取り持ってくれたのだった。「先生」には何度お礼とお詫びを申し上げてもすぎることはない。「先生」は、むかしから8ミリが趣味で映像や演劇に関しては今も興味を持っておられる。その趣味もあって学生の撮影を許してくれたのだと思う。
ひとしきりやりとりがあった後、「先生」が「今『パッチギ』を見てきました。かつての京都の雰囲気が鮮明に蘇るようでいい映画でした」と言われた。私は予告編しか見ていなかったので、その時には何も言えなかったが、これはきっといい映画だと確信した。
こういういわく付きの映画だが、確かに京都のあちこちでロケがおこなわれている。
東福寺周辺、銀閣寺哲学の道、新京極界隈、出町、総合資料館などがが、朝鮮高校だけは、出身者によれば、比叡山高校で撮影されたとのこと。
映画は、ある市立高校と朝鮮高校が友好のためにサッカー試合をしようという提案を持っていった男子生徒が、吹奏楽団メンバーの一人の女子学生にあこがれることから話がはじまる。彼女が演奏していた『イムジン河』に惹かれて、その歌と彼女への思いが在日問題をうかびあがらせる。
この映画を見た私の大学の学生が、「あの映画では高校生が喧嘩ばかりしている。あんなに喧嘩ばかりなんて信じられない」と感想をもらしたことがある。確かに今ではこういうことはなくなったが、1960年代終わりの時期には実際にあってもおかしくなかった。歓楽街や観光地では時々こうした風景を目にしたことがあるし、そうした行動こそが一方での若者の象徴であった(他方は、大学紛争や抗議行動であった。)また、関東では信じられないほど関西では在日問題はもっと身近で、かつ深刻だった。団塊の世代がまさにその時代なので、私はそれよりも少し遅れたので、そういう雰囲気が残っていたという体験しかない。
『イムジン河』がメジャーから発売されてからは、この歌は政治の渦に巻き込まれて不幸な歩みを辿ったが、若者の中には長く歌い続けられた。心にしみ入るいい曲だと思う。歌詞の日本語訳を作った松山猛をモチーフにした映画の主人公をはじめ、配役は日本人も在日も混在しているのがいい。フォーク・クルセダースの名曲をバックに京都の風景が流れると、高校生だった頃、大学生が輝いていた思い出と同時に、当時の差別の深刻さも蘇ってくる。
私は、自分の過去のある時期が最高だとは思ったことはないし、常にこれからが最高だと思って生きたい。ただ、やはり若かりし頃の雑然としながらも、躍動的な時期は捨てがたい。もちろん、その時期には私自身が精一杯生きていたかというとそうではなかった悔いが残る。むしろ、その悔いがあるからこそ、これからの可能性に賭けたいのかもしれない。
いずれにしても、自分を振り返らせてくれるいい映画に遅ればせながら追いついたのであった。
そうそう、ボブディランの『ノー・ディレクション・ホーム』http://www.imageforum.co.jp/dylan/index.htmlにはまだ行ってなかった。予定に入れておかないと。


![パッチギ ! スタンダード・エディション [DVD] パッチギ ! スタンダード・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31VN062AV4L._SL160_.jpg)


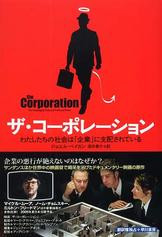

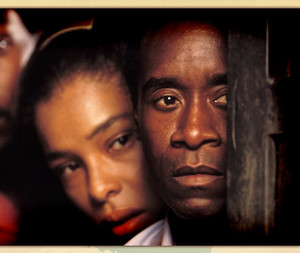
![マイ・ファーザー 死の天使 [DVD] マイ・ファーザー 死の天使 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PGJP59M0L._SL160_.jpg)

