遅ればさながら、『北斗の拳』山本プロデューサーのさわりの部分の授業をアップします。
「生き方としての編集者」と「素敵なウソは、人生を楽しくする」という名言が入っています。
積極的に楽しみを求めながら、それを引き寄せて人生を歩んでいく姿勢が次々と新しいチャレンジとなっています。
遅ればさながら、『北斗の拳』山本プロデューサーのさわりの部分の授業をアップします。
「生き方としての編集者」と「素敵なウソは、人生を楽しくする」という名言が入っています。
積極的に楽しみを求めながら、それを引き寄せて人生を歩んでいく姿勢が次々と新しいチャレンジとなっています。

ある大学で新入生対象で発想法を教えている。
初年次演習を学部全体で取り組んでいる知り合いから頼まれて講師に加わっている。講師依頼の折りに、先方から筒井独自の教授法ではなく、先方の大学の教授法で教えてもらいたいということがあった。
以前ならばこのお願いには少し戸惑ったことと思う。しかし、科目担当教員が統一した指導をおこなう必要性を痛感している者としては、私自身もこうした経験を積んでおくことが必要だと思ったので、喜んでお引き受けした。毎年新しいことに取り組むことで、自分のスタンスを常に時代に合わせておきたいと思うので、これも今年のチャレンジだと考えている。
授業シラバスは、以下の通りである。
「文章の要約とまとめ」以後は、これまでいつも実践していたので、困らない。しかし、それ以前のアイデアの拡散・収束は、授業としては初めての経験である。かねてから、この部分をどう改善するかを考えていたので、初めてながらも興味が尽きない。
最初に教員が受講生の前でデモを見せて、翌週からクラス内で受講生が実践することになる。教師としての力量は、クラスでの実践の時に明確となる。
ブレインストーミングがうまくいくグループとそうでないグループがあるし、ある時期に行き詰まるグループもある。この時にどういう対応を教員がするのかである。先輩教員にこれについて尋ねると、「ブレインストーミングでは、行き詰まっても教員は何も言わないことがいい」との答えだった。そこで、一度目の実習は不安になりながらもうまくいかなくても放っておいた。翌週二度目のブレインストーミングをおこなうと、受講生は以前よりも発想が出てくるようになった。これを見て、確かに言われた通りだなあと思った。
発想法の授業をおこなう時には、教員はあまり詳しく説明したり助け船をだしたりしないことが重要だ。しかし、それでもクラスによって差が出るのは何が原因なのか?
学生側の原因を除外するとすれば、やはり教員がクラスの雰囲気をどう作るかだろう。学生をリラックスさせ、気楽な雰囲気を作り上げて、彼ら自身が動き出す仕掛けを準備しておくことだと思う。
ありがたいのは、他の教員が互いに協力しながら教育しようという雰囲気があることである。授業後、教員が集まって、次回以後の授業について打合せをするのだが、これが実にスムーズに進んでいく。おかげで初対面の私であっても、質問もしやすいし、他の教員が以前の経験を丁寧に教えてくれるので助かっている。
授業は、かつて教員一人の独占物であった。しかし、そうした弊害が目立ち始めたことで、教員間の連携を進める科目(必修科目が多い)も増えてきた。その渦中に自らがいることが非常な刺激になっている。自分独自の教授法と統一的な教授法の双方ができる経験は、今後に大いに生かせることだと思う。

昨日、「広告表現技法」第二回の授業があった。
講師の石川さん以外に、ゲスト講師が多数の方がこられて、「北斗の拳」の制作および広告の手法についてきわめて率直に語ってくれた。ゲスト講師は、「北斗の拳」制作会社関係者など三名と大手広告会社からも一名の計四名であった。
制作会社『North Star Pictures』の山本秀基取締役、宮直樹部長、コアミックス社飛田野 和彦課長、電通営業部志村武彦さんが自分の人生を重ねながら、コンテンツについて語ってくれた(宮さんがかつて取り組まれた仕事は、先日ラジオカフェでイベントを一緒にした上田さんとつながっておられることがわかってうれしかったが、ここではその説明は省略する)。
山本さんは、若い頃から、自分が会いたい人ややりたいことをノートに書き留めていて、それを見ながらアンテナを張っていて、これまで自分の思いをすべて実現してきたとのこと。
たとえば、20歳の時に、ある講演会で面白い話をしてくれた女性記者に自己紹介しながら、自分に文章を書かせてほしいと頼み込み、二週間後には大手新聞家庭欄に連載記事を書いていたこと。また、集英社編集部に所属していた時には、原哲夫さん、ビートたけしさん、小泉純一郎さんなどを担当したことや、できるだけ多くの職業に従事している知り合いを持つことを信条にしてきたなど、まさに生まれながらの編集者という人生を歩んでおられる。
仕事柄、マスコミ就職講座などの講師を引き受けることがあって、学生から編集者になる方法について尋ねられることが多い。その時、山本さんは、編集者は職業ではなく、生き方が職業であることが重要と言っているとのこと。
雑誌編集者は学生の希望職種である。大手メディアの編集者に就くには激戦をくぐり抜けていく必要があるが、就職自体を最終目標にする人はそこで終わる。むしろ、その先をめざす、いやそれ以前に生き方自体が編集者である必要がある。
しかし、就職してから編集の仕事をすることよりも、人と人とを結びつけ、そこから新しいブレイクスルーを起こすような生き方こそが編集者には最も必要である。とすれば、編集者とは、雑誌・書籍などの教義の編集者だけではなく、職種にこだわらない生き方自体となる。
文章であれ何であれ表現し、それを他人の目にさらし、それを糧にして次をめざす。そうした実践なしには編集者ではありえない。大作家が書けなかれば、編集者自身の作品を差し替えするくらいのクリエーターとしての実践が必要だ。
山本さんの話を聞きながら、途中からは、自分の人生を振り返り、私自身にも突き刺さった。山本さんのおうような風貌とは別に、話された内容は人を惹きつける。もちろん、北斗の拳は魅力的なテーマであったが、それをプロデュースする山本さんの魅力がそれを倍加させていると思う。今回の講義に終わらず、これからも継続的な話をしていきたい。
この講義の非常勤講師である石川さんは、毎回、そして毎年新企画を考えてくる。
その一環でこれだけ多くのゲスト講師をお迎えして授業をおこなったが、一つの授業に専門家が五名も揃う授業は他にない。しかも、申し訳ない限りだが、自腹で参加して頂いたゲストもおられた。心からお礼を申し上げたい。
また、この授業を発展させられるかどうかは大学の力量が問われるところである。いい試練だと思う。
「大学はまだ生きている!」

昨日、ケンシロウが精華大学にやってきました。
フィギュア制作で有名な海洋堂が精魂込めて作った精巧な傑作です。世界に二人しかいません。雨の中、高額の保険を掛けておいでくださいました(大学の特別の計らいです。感謝)。フィギュアファンに限らず、ケンシロウを一目見ようと集まった学生たちの人だかりが絶えません。
なぜケンシロウが来たのか?
それは、今週土曜日に北斗の拳プロデューサーが大学の授業にやって来るからです。土曜日の授業に向けて、受講生を中心に広告が展開されています。人文学部の授業ですが、受講生以外、他学部生でも、また学外の方でも大歓迎です。
この授業については、このサイトをご覧下さい。ケンシロウ登場に関して面白い記事を投稿している学生もいます。いよいよノッてきました。
13日(土曜日)午前10時40分〜午後4時10分
精華大学黎明館(れいめいかん)L-201号室
当日、サプライズもあります。
大学までの経路は、地下鉄でも叡電でもどちらでも可能です。

わが国最大の独立ジャーナリスト集団アジアプレス大阪事務所が、活動報告をする。現地取材したメンバーによる撮影映像を交えて、話が進行するが、今回はライブ感を強めるためのを準備している。たとえば、イラク報告では、現地と電話でつないで質疑応答をする。北朝鮮報告では、脱北女性の証言を交えている。
(昨日、アジアプレスの方から、講演者に綿井健陽さんも参加されると連絡があった。玉本・坂本さんは、イラクのクルド人地区に、綿井さんは首都のバクダッドに滞在していた。イラク全体の動きをとらえるためには、ますます豪華な組み合わせとなった。)
前回のブログでは、ラジオカフェのイベントがジャーナリズムばかりでよくないと言っているので、矛盾するように思われるかもしれない。しかしむしろ、両者が存在してこそ発信メディアとしてふさわしいからだ。個人的には、どちらも好きだし、違いのよさを吸収したい。
アジアプレスと精華大学とは、人文学部社会メディア学科が設立された時からつながりがある。もちろん、それ以前にもつながりがあるが、大学の授業に関わってもらうことで新しい魅力を知ることができた。それは、ビデオアクティビストとしての彼らの活動とは違った、初心者に向けた彼らの目線を実感できたことである。
ただ、非常勤講師の方の授業は、その実力と熱意に支えられているために、満足度の高いものである。しかしながら、かれらの授業は、他の授業との関連性もなく、また教育カリキュラム上での位置づけもはっきりしない。孤立した授業であることが多い。しかし、それでは単に講師の知名度や経歴に依存しているだけで、大学教育の変化をもたらさない。
その状況を変えようと、精華大学人文学部では、非常勤講師の方の授業も他の授業と関連させるようにしている。
具体的には、いくつかのフェーズで進んでいくことになるが、
である。
実は、ラジオカフェのイベントと学内でのアジアプレスのイベントが重なり兼ねなかったので、ラジオカフェイベントから一時的に降りたのだった。しかし、結果的に後者のスケジュールが延期されたので、ラジオカフェにも加われることになった。
以下にお知らせしている、5月12〜13日のアジアプレス報告会は、精華大学のイベント以前に決まっていたのだが、前座的な意味で精華大のイベントを考えていたのだった。昨年度授業を担当して頂いたアジアプレスのジャーナリストが精華大生にもボランティアで手伝う機会を与えてくれた。そこで、何名かの学生がはせ参じている。
12〜13日の報告会が少しでも多くの方に関心を持って頂けるように、アナウンスをしようと思う。是非ご参加下さい。
以下が、報告会の詳細です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アジアプレス 最新現地報告会のお知らせ
独立ジャーナリストのネットワーク、アジアプレスは、世界各地の現場で、取材活動を続けています。
今回、イラク、北朝鮮に焦点をあて、大阪で現地報告会をおこないます。フセイン政権崩壊から3年。いまも混乱の続くイラクで、人びとは、どんな思いで日々をおくっているのでしょうか。
情報統制の厳しい北朝鮮内部のことは、なかなか外に住む私たちには見えません。抑圧と貧窮の中で、一般の民衆は何を望み、どのように暮らしているのでしょうか? 最新の現地取材の成果を、映像をまじえて報告します。とりわけ、社会の弱者である女性と子供の現状に力点をおきます。北朝鮮、イラク内部と電話で結び現地のナマの声を伝える試みもおこないます。(通信回線の状況次第)。また、北朝鮮を脱出した女性に体験を語ってもらいます。
主催:アジアプレス・インターナショナル
共催:ウェブジャーナル・アジアプレスネットワーク(APN)
女性ジャーナリストの会
協力: デイズジャパン・関西サポーターズクラブ
1. <5月12日(金)>
混乱つづくイラク 〜映像で見る、女性・子どもたちの現状〜
■玉本英子
イラクの女性、子どもたちの現状、イラクのヒロシマ、ハラブジャはいま
■坂本卓
武装勢力はいま
■綿井健陽
バグダッド最新報告
■バグダッドをつなぐ生電話インタビュー
〜参加者のご質問にバグダッドから現地スタッフが答えます〜
2.<5月13日(土)>
北朝鮮はどうなっているのか 最新現地報告〜女性・民衆の苦難の現状を考える
■第一部 石丸次郎 内部映像による報告
■第二部 脱北女性が語る、北朝鮮の女性たち
★Aさん 55才 2004年ハムギョン北道より脱北、日本入り
とき 2006年5月12日(金)イラク現地報告会
2006年5月13日(土)北朝鮮取材報告会
時間 両日とも 午後7時〜9時(午後6時30分開場)
場所 ドーンセンター 4階 大会議室(5月12日)
5階 特別会議室(5月13日)
※料金 1000円
ご案内 http://www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html
JR東西線「大阪城北詰」駅2号出入口より西へ550m
京阪・地下鉄谷町線「天満橋」駅1番出口より東へ350m
市バス京阪東口からすぐ
大阪市中央区大手前1-3-49 TEL:06-6910-8500
■ お問い合わせ TEL06-6373-2444(アジアプレス大阪事務所)
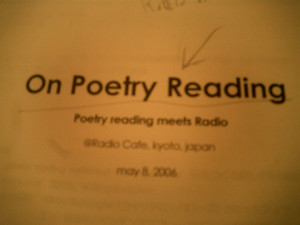
メディアに関わる中で、私のスタンスに変化が出てきた。
元来が法学部出身なので、ジャーナリズム的な視点や海外報道には慣れ親しんでいる。もちろん、あくまでもそれを研究材料にしていたにすぎないのだが、身近なジャンルとなっていた。しかし、現在では、そこからウイングを広げている。
京都三条ラジオカフェでは、毎月第一月曜日に例会が開催される。
毎回のテーマは少しずつ違いがあるにしても、主催者にはマスメディア出身者が多いことからどうしてもジャーナリズムに固定しがちである。もちろん、そうしたテーマは面白いし、今後も継続すべきだが、そのことがフォーラムの参加者を固定化しがちである。
こうした事情もあり、また私自身の視野も広げるために、5月の例会のテーマは、ワークショップで参加者も楽しもうということである。普段は、講演者だけが説明して、参加者はそれを聞いて質疑応答するという関係が固定されている。しかし、今回は参加者自身がつながる仕掛けを準備した。この一ヶ月、何度か会議やリハーサルをしながら、当日のイメージをふくらませている。
第一部は、poetry readingで詩人が詩を作る楽しさを語りながら参加者と一緒に作り上げる。第二部14分間がラジオ番組自体を生放送する。そこに第一部で出来上がった詩を絡ませる。第三部では、講師の上田さんが歩んできたセサミストリート、テレビ、そしてラジオの世界への広がりを体験する。
全体は三部構成であるが、各部は、次の部とレイヤーを組み合わせるようになっている。しかも、途中のライブ放送を交えながらワークショップをおこなうという、ワークショップの手法としてもかなり斬新な試みである。上田さんと私は、同女大だけでなく、精華大の学生と私でも同様の企画が展開できることである。そのために、スタッフの経験と視点を深めることにある。
当初は、上田さんと一緒に私も登壇することになっていたのだが、別企画が重なってしまって、私は登壇しなくなった。その後、別企画の日程が変更になって参加できるようになったのだが、既にプログラムが確定しており、今回は制作側に回ることになる。残念。
なお、上田さんの紹介は、Appleの教育サイトにもある。(彼は、ハーバード大学に留学している1984年に、ボストンでMac World BostonでMacintosh発売を目撃して以来のマックユーザである。)
是非ご参加下さい。
参加の場合には、主催者にメールをお送り下さい。
では、お楽しみあれ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
三条御幸町メディアフォーラム 第21回月例会
「“radio on radio” radio as playful media
-ラジオでワークショップをやってみよう-」
●日時●2006年5月8日(月)午後7時〜9時(開場 午後6時30分)
※月例会後、引き続き懇親会(二次会)を予定しています。
●場所●京都三条ラジオカフェ店舗(三条通御幸町角1928ビル1階)
●お話●
□上田信行
同志社女子大学現代社会学部現代こども学科教授。ハーバード大学教育大学院修了。
Ed.D.(教育学博士)。学習環境デザインとメディア教育についての実践的研究を行う。
NHK「おかあさんといっしょ」の開発チームに加わるなど「ラーニング・アート」をキーワードに
さまざまなプロジェクトに関わる。奈良・吉野に実験的アトリエ「ネオ・ミュージアム」を
創設し、多数のワークショップを開催。
□出口朋美(むらさき)
追手門学院高校英語科非常勤講師・詩人。
関西大学大学院外国語教育学研究科博士課程前期課程修了。
第17回新風社「ギフトブック・詩のコレクション」優秀賞受賞。
花形朗読詩人会会員・Kyoto Spoken Words Slam出場。
●プログラム●
今回のラジオカフェ・メディアフォーラムはワークショップ形式で試みます。
19:00〜21:00までの2時間のワークショップは3つに分かれており、2つのワーク
ショップの間に14分間の生放送があるというおもしろい構造になっています。
18:30-19:00 開場、カフェタイム
19:00-19:40 “poetry reading” workshop 詩をつくる楽しさを体験しよう!
内容要約:William Burroughs(ウイリアム・バローズ)のカットアップという手法
を使い、参加者の方々に詩作を体験していただきます。その後、グループで完成させ
た作品の展覧会を行います。
19:45-19:59 番組放送「詩がラジオと出会ったら」
内容要約:インターネットラジオ、Podcastingなどで、ラジオというオールドメディ
アが、先端表現メディアとして活躍しています。今回はポエトリーディングをコンテ
ンツにその可能性を探ります。
20:00-21:00 ”after the radio” workshop
内容要約:セサミストリートから、ラーニングアートへ 上田信行のメディアストーリー
1)セサミストリートとワークショップ
2)MIT Media Labとモチベーション研究
3)表現、詩、そしてラジオ!
■参加費 月例会 一般1,000円 学生500円(1ドリンク付)
懇親会 一般2,000円 学生1,000円(飲食代)
※定員25人先着順。
参加お申し込みは「三条御幸町メディアフォーラム」事務局まで。
Tel.075-254-8556 Fax.075-253-0323 e-mail mf@radiocafe.jp
〒604-8082 京都市中京区三条通御幸町角1928ビル1F
京都ラジオカフェ株式会社気付

大学において教育・研究に携わっている身としては、直接教育対象となる学生はもちろんのこと、社会とつながった戦略をとることが必要だと思っている。
元来の専門が第二次世界大戦後のドイツ外交史であったが、やがて紆余曲折を経て、メディア、インターネット、NPO、大学教育を専門にすることとなった。以前であれば、「私の専門は、国際関係論です」とか、「ドイツ外交史です」と言えたが、現在は四つを並べている。
すると、「あなたの専門はなにかわからない」と言われる。日本語表現法の授業では、「相手に一言でイメージできるように語りなさい」と言っている建前からすると、矛盾していると言われてもしようがない。この点は悩み続けている。
しかし一方で、「自分を一言で語られたらおしまいだ」とも思う。「筒井さんは、国際関係論が専門の方ですね」と言われると、伝統的な専門分野の一員であるという若干の満足感とともに、「それしかできない学者バカ」と言われている気もする。
もちろん、学者のキャリアとしては専門が一つの方が王道だし、職を得るためにはその方がはるかに楽だ。教員採用システムは、一つの研究分野に該当する教員から該当者を選択するのが一般的である。そこでは、すぐれた研究業績(論文、報告書、学会報告など)を持つ該当者から絞っていくのであり、研究業績の質と量が物を言う。(最近では、研究業績だけでなく、教育経験なども選考対象になっているが、前者なしで後者だけで採用されるとすればもはや大学教員の質の保証はできなくなる。)
一研究分野での業績だけで研究者の力量が判断されるとすれば、多分野の専門分野を持つことは完全に不利である。他の専門分野の業績は香料の対象にならないからだ。「だからこそ、一分野で業績を積む方が確実である」ということになる。一研究分野やその分野のステイタスの高い学会での活躍が好まれるゆえんはここにある。
私の場合、その不利は十分すぎるほどわかっている。王道を進めればいいが、私にはできない。理由は、「多くの分野に取り組んでいる方が面白いから」だ。誰かに強制されていたりする場合、その強制がなくなると取り組まなくなる。しかし、私の場合は、自分から飛び込んだ世界であるし、取り組んでいたらやめられなくなった。そこで、結局、10年以上前から新しい取り組みをしていたものを捨てることもなく、積み重なって現在に至っている。
で、「筒井さんの専門は何?」ということになる。
私も相手に合わせて、「私の専門は、Aです」というが、「その他にBやCもやってます」と付け足しのように言うようにしている。
昨日から始まった授業「広告表現技法http://blog.ishijun-seika.net/」も私の新しい可能性を広げる試みである。
私が担当する授業ではないが、側面から育ててきた授業であり、大学にとっても売りになるし、学外からも注目すべき価値があると思う。今年六月の学会でこの授業について取り上げる。
特に、
に限定して報告するが、現在の大学の授業では、特筆すべき経験を積んでいる。
詳しくは、また紹介する。

先週末は、春の学会報告用予稿集原稿二本と、共著本の企画書の原稿を仕上げた。まだもう一本残っているけど、なんとか山を越えた。文章を書くのは、主張するコンセプトさえ明確であれば比較的早く書けるようになった。しかし、話し言葉はまだまだだ。
まもなく出る編著本では、原稿執筆とともに、座談会もおこなわれた。原稿は問題なく書けたし、2月に行われた対談も楽しかった。しかし、対談のテープ起こし原稿を見たらとても読ませる言葉になっていなかった。同じ修飾語が多用されたり、回りくどい言い回し、言い直しが鼻を突く。
論旨を直すつもりがないにしても、表現は大幅に直しが必要だ。出版社にご迷惑をおかけすることになる。ただし、座談会の他のメンバーがいいので、気楽に話をさせてもらい、それなりに意味のある話をしている。不幸中の幸いである。読者にとっては、出版前のことは関係ないので、その点は助かる。
しかし、今後座談会や対談がある時のことを想定して、話し方を工夫をしないといけない。今日は、卒論の個人面談であるが、自分が話す言葉を反芻しながら、無駄な表現をなくすようにしてみた。少し窮屈だが、しばらくの間、書くように話すことを心がけよう。
ここまで書いてから、座談会の音声を聞いた。自分の発言を音声で聞いたが、聞いてもそんなに聞き苦しくない。もちろん、自己弁護的な部分はあると思うが、それにしても文字で読むほど違和感はない。書き言葉と話し言葉の違いと改めて実感した次第だ。
さらに、今夜、ラジオカフェで五月例会のリハーサルをした。
これまで講演会形式が主で、ワークショップ形式は初めてなので、リハーサルにも力が入る。司会者は、ワークショップの専門家だが、ラジオのDJは初めての体験だ。しかし、うまい。なによりも、展開が早いし、言いよどみがないので、聞いていても疲れない。ここまですごいレベルのしゃべりを聞くと、座談会での自分のしゃべりの不十分さを痛感する。
話し言葉一つで、安心したり、落胆したりを繰り返しを経験した日であった。
このワークショップの模様は五月例会の後に発信する。

つまり、一年生向けのプレゼンを文字だけで制作すると1時間、文字+音声だと3時間、それが文字+音声+動画になると7時間になる。「皆さんは、3分間のプレゼンのために、7時間を費やす覚悟はありますか?
と問うた。この反応がどれだけ彼らの切実感に結びつくかが楽しみだ。もっとも、教員にとっては、二度目のプレゼンだったので、受けはあまりよくなかった。う〜ん、このあたりが私の反省点だ。
では、お聞き下さい。
今日は、二回生向けのゼミ紹介があった。学科教員10名あまりが各5分間でゼミ紹介をするという企画だ。私は懲りずに「高橋メソッド」の字体で、パソコンによるプレゼンをおこなった。
二回生にとっては、まずまずの反応だった。
私は、メディアに興味がある学生であっても、テレビ番組や映画を見るのが好きな学生でなく、むしろそれを制作する側の視点を持ってほしいと訴えた。見る側にとっては、コンテンツを見ることは気楽に見ることができるにしても、制作側がいかに大変かを私自身のプレゼンビデオ製作時間にたとえた。