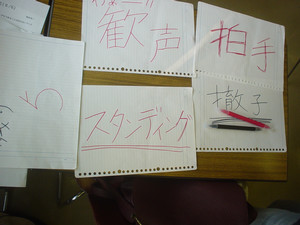筒井のコメントを聞く
↑
(ダウンロードするか、iTunes for mac/winで見てください。)
シンポジウムの続きである。後半のディスカッションのおける私の発言をアップした。
私のプレゼンファイルは、ここにある。ラジオ番組制作プロジェクトの動画ファイルは、過去のブログ(5月23日)に掲載されている。
前半のパネリストの報告を終えて、後半のディスカッションに移った。だが、「二つの学び」のアプローチは微妙に異なる。この相違点がおもしろい。ここでは、論点を三つに絞る。第一の論点は、学習手法の範囲や多様性である。たとえば、陰山さんは、生徒の学力を向上させるためには、あらかじめできるだけ範囲や手法を絞り込んでおけば、学習プロセスと上達度が計りやすい。このことが生徒の「やればできる」という自尊心を勇気づけることになり、結果的に生徒が「意識せずに」学習することができる、と説明する。
学習者に学びを意識させないという方法は、最近の脳科学でもよく言われる。これは、消費者に広告の意図を意識させないで商品を買わせるという手法と同じである。脳科学者の川島隆太さんが陰山さんを評価する理由がよくわかる。陰山さんの前任小学校での授業風景を映像で見せてくれたが、生徒は陰山メソッドを強いられているという気持ちはなく、互いに励まし合いながら進んでいるところがいい。ただ、その逆に、彼の授業は、教師による一斉授業方式であり、生徒の自主性や自律性は絞られた手法の中に限定される。
これに対して、苅宿さんの「能の鏡」ソフトや私が見せたようなラジオ番組制作ワークショップは、多様な役割とそれを相互に意識する全体性(俯瞰性)が前面に出る。MC、ディレクター、タイムキーパー、撮影担当者などがそれぞれの役割をこなしながら、全体を見る視野が養われ、実践体験から体得する達成感は大きい(もちろん、うまく行かなかった時の喪失感も大きい)。しかし、逆に、全体性の視野が獲得されたとしても、それをより深い学びへとつなげることが難しい。
単純に比較すれば、陰山メソッドはその手法に入り込めれば効果が大きいと思うし、わかりやすく、単純であるがゆえに商品開発が容易であり、保護者や消費者にも受ける。逆にわれわれの実践は手間がかかる上に効果の変動が激しい。その点は正直に告白したい。ただ、学びの習得は、教師の一斉方式よりも生徒・学生の参加方式の方が有益であり、陳腐化する知識の習得よりも、体験と相互の連帯性に意味があるという知見が得られてきたはずである。
ただ、実際的には、有能な教育者が実践すれば両者の差はほとんどない。しかし、そのメソッドが文部科学省、メディア、企業、教育界を巻き込んだ大運動となるに至って、当初の意図とはかなり異なってきている。その傾向を批判することはたやすいが、私自身の信条は批判するよりも自らの活動や研究によって成果を明らかにしていくことである。1993年、前任校で言語表現科目を新設する時にも、守旧的な批判にさらされながらも、批判よりも実行を旨としてきたのである。
次の論点は、コンピュータの活用方法である(この点について、問題提起する時間がなかった)。コンピュータは、情報を計算するツールである。電子計算機という言葉はそれを物語っている。これは検索エンジンやネットワーク管理の複雑化にともなって今日ではさらに重要になっている。しかしながら、教育におけるコンピュータの活用においては、計算機能としてのコンピュータを重視する限りは人間一般には普及しない。
むしろ人間のコミュニケーションを広げるツールとして使われてこそ意味がある。それは、計算機能を前面に出すのではなく、後景に忍ばせて置くことである。Webからblogへの変化は、一般ユーザがシステム構築する手間を省いて、コンテンツ自体に精力を注ぐことで爆発的な伸びを示していることが物語っている。私は、このように多様なコミュニケーションをサポートするツールとしてのコンピュータの活用に教育の未来がかかっていると思っている。
その点では、陰山メソッドにもとづくゲームやPDAなどのソフトは、計算や答えを即答するように、計算機能を高度化させる方向に進んでいる。こうした分野のソフトやハードウエアしか開発されない現状は残念である。。コミュニケーションをサポートするソフトやシステムがさらに一層の発展を迫られていることを痛感した次第である。
最後に、二つの学びに関する議論に終始することは、現在、こどもや若者が置かれている現状を変えることにはならないことである。陰山さんも小学校の事例を上げながら、こどもの存在を無視する現状に懸念を表明されていた。私もこの点に同意する。
ただ、今の教育論議が、階層や格差の二極化傾向の深刻化に気づきながらも、上の極での競争心をあおり、エリート的な生徒や学校の育成には大変熱心である。だが、その一方で、下の極への配慮はむしろ切り捨てられていると言っていい。そこにこそ最大の問題があると思う。この点の改善のための議論こそが今後継続されるべきである。
これら三つの課題とは別に、シンポジウムの最後に、私は次のようなコメントをした。これは、拙編著『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』のなかで、仙台みやぎサポートセンター代表の加藤哲夫さんが述べられたことを引用しながら発言を締めくくった。
つまり、知識を習得することや論理的な文章を書くことは、それができる人間はいいにしても、実はそのことは、それができないが別の能力を持った人間を排除することになっている。近代社会は、専門用語を駆使して、論理的な文章や説明ができる人が特権的な地位に就く社会である、という加藤さんの指摘である。これは、イリイチの「脱学校化社会」の指摘ともつながる。もっとも近代社会を否定するまでいかなくても、論理性や専門知識の習得だけを追求する教育の弱点を考える必要はある。話が大きくなりすぎるきらいはあるにしても、教育の原点を考える上でわすれてはならない問題である。
以上、シンポジウムおよびそれ以外でのやりとりを踏まえて、三つおよび追加的な論点について論じた。
シンポジウムが終わって、すぐに立命館を離れようと思ってタクシーに乗ろうと思ったが、たまたま立命館小学校に行こうとした陰山さんに出会った。そこで、一緒にタクシーに乗っていった(タクシー代は、気前よく私が払ったよ!)が、お子さんとの距離を保つことには苦労されているとの話を聞いた。教育問題のオピニオンリーダーであるがゆえのつらさであろう。
陰山さんと議論して少しは理解が深まったが、正直言って教育観の相違はかなり大きい。その溝を埋めることは難しいと思うが、それにもかかわらず、子供、保護者、地域とのつながりを大切にして教育されている姿勢には学ぶべきことは多々ある。さらにすぐれた実践や研究をすべきなのである。