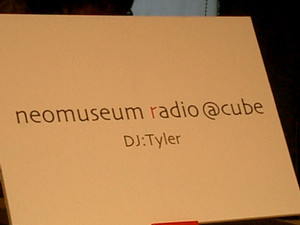昨日、吉野でおこなわれたParty of the Futureに参加した。
http://www.nobuki.jp/pofpof.html
参加者も多様であるが、出し物も多様である。
神戸芸術工科大学の学生は、建物の外の庭と建物内のスタジオにビデオ撮影機材を設置して、10分毎に10秒撮影して、人の動きを撮影していた。準備から開会、さまざまなイベント、そして終了の全過程を収録し、最後に2分間のダイジェスト版を参加者に見せた。カメラを意識していない参加者の動きは面白い。
初めての参加で緊張して入ってくる参加者の姿、ネームプレートに一心に書き込む様子、ひたすら食べ続けていたり、二階にいるDJが一階の参加者を盛り上げる様子を上から撮った様子など、人が集まったり、動いたりした姿を早回しするとまさに映画のようだ。
この様子は、最終的にはデザイン学会で報告するそうだが、その時には、Flashムービーとして、屋外と屋内とを同じタイムラインにして同時に見るようにするそうだ。参加者の出会いを促進するために、主催者が適切なコンテンツと仕掛けを準備したところで、参加者がどのようなコミュニケーションの交換や流通をおこなうのかを見るそうだ。
中京大学の学生は、大学のサーバに、同じくFlashで作った、宇宙に浮かぶ地球から、地球にどんどん近づいていき、最終的に吉野まで到達する。そこに、参加者が携帯電話で撮影した会場の面白い写真を送ると、CGIを使って、二分ごとに次々の送られてきた写真が浮かんで来るという仕掛けだ。リアルタイムでFlashを見せる新しい試みだ。
東京芸術大学の院生は、100枚のTシャツをすべて手書きで描いた。そこには番号を振ってあって、参加者がくじを引いて会場にあるシャツを見つけ、体にまとう。このシャツは番号順に連続的な絵になっているという、フィナーレでは、番号順に並んだ参加者を二階から撮影して全体の絵を確認した。
一品持ち寄りパーティーなので、和食、中華、エスニック料理と多種多様な料理が楽しめる。料理には作者が立てた
旗が差してあり、だれがどの料理を作ったのかがわかるようになっている。
参加者の中から、アーティストやプログラマーなどが登場し、Neo Museum Radioという企画で、DJが次々とゲストにインタビューするというラジオをまねたイベントもあった。ナムコの教育玩具製作者、お絵かきソフトプログラマー、パフォーミング・アーティスト、高校生などが登場。参加者からのエキスと取り出す試みだ。
オープニングとフィナーレは、主催者の上田信樹君の新曲披露だ。4月27日CDデビューとのこと。
http://www.nobuki.jp/release.html
ポップな感覚のノリの良い曲で参加者が飛び上がりながら楽しんだ。
いつもながら思うのだが、参加者がいいということだ。
上田信行さんが、先日、別のシンポジウムで次のように言ったそうだ。「最近は、ソーシャルネットワークシステムという招待制の人と人との出会いを楽しむツールが大流行だが、私は10年以上前からこれをやってきた。つまり、パーティーを企画することで、主催者の知りあいか、その知りあい程度に限定して、内容の濃いイベントを実践してきたのである。オンラインであっても、オフラインであっても、メンバーを限定しながら、どのようにパーティを実践するかは人間のコミュニケーションの原点である」と。
主催者親子の様々な活躍が起点となって、徐々に子供に主体が移りゆく中で、新しい将来を予感させる試みである。
私の学生もここに参加して、彼らの企画を披露したいのだが、参加者もなかった。精華大の陶芸の学生が作品を披露していたのだが、私の学生の企画を見せたいものだ。
当日撮影した写真をアップした。
http://www.kyoto-seika.ac.jp/tsutsui/friend/NeoMuseum/index.html