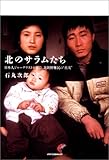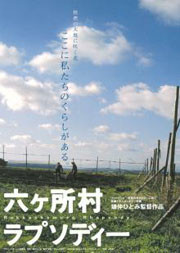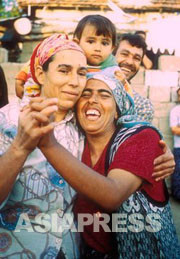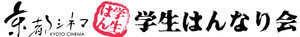ロハスな生き方を訴える坂本龍一は、最近、政治に関わっている。もちろん、9.11事件の時にも、時流に抗して『非戦』という本を出版いたのだけれども、最近は、青森県六ヶ所村のプロトニウム再処理工場設置反対の国際的なキャンペーンを張っている。
彼のサイトのトップには、六ヶ所村再処理工場設置反対キャンペーンのサイトがリンクされている。
文化の日には、彼の番組にゲストで登場した映画監督鎌仲ひとみさんの映画「六ヶ所村ラプソディー」とトークイベントが開催される。場所は、NPOやアートの拠点のお寺應典院だ。ここは、言わずとしれた、秋田光彦住職と主幹の山口洋典さんがプロデュースしている。
鎌仲ひとみさんは、米国の独立メディアの先駆けであるPaper Tigerに所属していたこともある、市民メディアの映像クリエイターである。原爆やシリアスなテーマを扱いながら、社会との対話を図っている。先日、大学で講演していただいた玉本英子さんは、つい先日、東京で鎌仲ひとみさんとシンポジウムで同席したとのこと。そういえば、「SOBORO DIALOG」のゲストで参加されたREALTOKYO / ART iT発行人兼編集長の小崎哲哉さんも坂本龍一さんのことを話題にされていた。私にとっては、知り合いを通じた数珠繋ぎのつながりでイベントに参加することになった。
是非ご参加ください。
應典院コミュニティシネマシリーズVOL.8
鎌仲ひとみ監督作品「六ヶ所村ラプソディー」大阪劇場公開記念イベント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「映画が地域を見つめる・映画で地域を見据える」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www.outenin.com/ccs/008.html
本企画では鎌仲ひとみ監督をお招きし、イラク訪問をきっかけに知った内部被ばく、世界を取り巻く核の脅威、映画「ヒバクシャ」制作当時のエピソード、そして映画「六ヶ所村ラプソディー」制作に至るまでの流れを映像とトーク、ライブを交えて紐解きます。まず第一部では「六ヶ所村ラプソディー」の導入とも言える映画「ヒバクシャ」をじっくりご覧いただきます。続くランチタイムには、下北半島産の昆布を使った料理や、青森県産の地粉を使った天然酵母パンなどを用意します。また、第二部ではCYCLUBとのトーク&ライブ、第三部では同志社大学大学院との協働トークセッション、そして第四部では。これらの変化に富むゲストと共に、ウラン採掘から原子力発電、劣化ウラン弾の使用から核廃棄物の行方としての再処理、廃棄物処分、という核を取り巻く社会のシステムとスタイルを見つめ、ひとりひとりの生活や暮らしの中の選択、そして地域社会のあり方を見据える場と機会といたします。
[開催概要]
■日時:2006年11月3日(金・祝)9:30〜21:30
■プログラム:
第一部 10:00〜12:00 映画「ヒバクシャー世界の終わりに」上映
もうひとつの被ばく「低線量被曝」。この問題に焦点を充てた映画
「ヒバクシャ」をご覧いただきます。なぜ監督が「六ヶ所村ラプソディー」
を制作するに至ったかを感じていただきます。
第二部 13:00〜15:45 映画「六ヶ所村通信 no.1」上映とトーク&Cyclubライブ
撮影現場からの報告を兼ねて作成された「六ヶ所村通信no.1」を上映。
監督には「ヒバクシャ」から「六ヶ所村ラプソディー」に至ったいきさつ
などをお話いただきます。そして、トークセッションを行います。
トーク終了後にはCyclubによる30分程度のライブ演奏があります。
第三部 16:00〜18:15 映画「六ヶ所村通信 no.2」上映とシンポジウム
「六ヶ所村通信No.2」上映の後、同シリーズを作った理由やいきさつなどを
監督にお話いただきます。後半は「六ヶ所村から『地域におけるソーシャル・
イノベーション』を考える」(共催:同志社大学大学院総合政策科学研究科)
と題し、鎌仲監督と共に「地域社会のあり方」を語り合います。
第四部 18:30〜20:45 映画「六ヶ所村通信 no.3」上映とトーク&岡野弘幹ライブ
「六ヶ所村通信no.3」上映の後、監督によるちょっとした裏話のご紹介を。
後半は、映画『ホピの予言』などで知られる辰巳玲子さんと、音楽家であり
アメリカインディアンムーブメントを日本で支えてきた岡野さんをゲストに
地球人の精神について語り合います。トークの後には岡野さんのライブ演奏有。
■参加費:各プログラム 1,000円(学生700円)
全日パスポート3,000円(学生2,000円)
*参加予約はメール、FAXで受け付けます。
なお、同志社大学大学院総合政策科学研究科の教職員・学生は無料。
應典院寺町倶楽部会員は学生割引と同額での優待参加をいただけます。
申込予約多数の場合には当日入場をお断りすることがあります。
■場所:應典院本堂ホール 大阪市天王寺区下寺町1-1-27
http://www.outenin.com/otenin_6.html
地下鉄「日本橋」「谷町九丁目」徒歩8分
■定員:各プログラム毎100名
【事前予約受付有・開場時は全日パスポートでの参加者を優先入場】
■ゲストプロフィール:
鎌仲 ひとみ(映画監督・東京工科大学メディア学部助教授):第二部・第三部・第四部
http://www.g-gendai.co.jp/hibakusha/
http://www.rokkasho-rhapsody.com/
http://www.teu.ac.jp/info/lab/teacher/media_dep/83.html
1958年富山県生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。1984年、グループ現代や岩波映画制作所と助監督契約。1991年10月、文化庁芸術家海外派遣助成金を受けて、カナダ国立映画制作所で勤務。その後ニューヨークのメディア・アクティビストグループ、Paper tigerに参加。1995年に帰国しフリーの映像作家として活躍。「博士のさがしもの」(1990)、「戦禍にみまわれた子供たちー湾岸戦争8年後の子供達」(1997)、「心の病が癒される時」(1998)・「エンデの遺言―根源からお金を問う」(1999)、「がんを生き抜くー希望を支える医療の記録」(2001)など映像作品の他、『ドキュメンタリーの力』(2005、子どもの未来社)など執筆も多数。
Cyclub(サイクラブ):第二部
http://soundvision-tokyo.com/cyclub/
アメリカで生まれ・イギリス育ちの音楽変形変動アーティスト集団。ソニックユースのサーストンムーア、ダイナソーJrのJマスシスなどの前座を務める。米国マサチューセッツで誕生し、環境問題をテーマに掲げた演奏活動を英国ロンドンで展開。ライブ演奏と合わせて多彩なイベントも企画し、社会へ環境問題を訴える活動に取り組んでいる。バンドのCD売上金を資金に青森県六ヶ所村の核再生処理工場へ視察へ行き、その後も全国で投げ銭ライブを行いながら六ヶ所村再処理原発工場を止めるためにライブを実施している。
新川 達郎(同志社大学大学院総合政策科学研究科長・教授):第三部
http://sosei.doshisha.ac.jp
1950年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、同大学大学院政治学研究科博士後期課程修了。東北学院大学法学部助教授、東北大学大学院情報科学研究科助教授などを歴任し、99年4月から同志社大学大学院総合政策科学研究科教授。同研究科のソーシャル・イノベーション研究コースでは「ソーシャル・イノベーター」とよぶ地域公共問題解決に活躍する実践者であり研究者の養成に取り組んでいる。また、京都市市民参加推進懇話会委員、滋賀県新行政システム推進委員会専門委員など、よりよい地域社会を推進するための制度改革を牽引する。『行政と執行の理論』『行政とボランティア』『中央省庁改革』『比較官僚制成立史』など著書、翻訳多数。
秋田 光彦(浄土宗大蓮寺・應典院住職):第三部
http://www.dairenji.com
1955年大阪市生まれ。明治大学文学部演劇学科卒業。東京の情報誌「ぴあ」に入社し、主に映画祭の企画・宣伝を担当。退社後、映画制作会社を設立、プロデューサー兼脚本家として活躍。1997年に劇場型寺院應典院を再建。市民活動や若者の芸術活動を支援している。同寺は1999年大阪まちなみ賞、2003年なにわ大賞準大賞を受賞。また、應典院を含め、大化の改新以来、歴史、文化の魅力にあふれた上町台地界隈におけるまちづくりのネットワーク組織「上町台地からまちを考える会」の代表理事や「上町台地マイルドHOPEゾーン協議会」の事務局長なども務め、市民、コミュニティ、地域資源のあり方を具体的に提案し、実践する。共著に「市民プロデューサーが拓くNPO世紀」「宗教と人間の未来」など。
辰巳 玲子(ランド・アンド・ライフ主宰):第四部
http://www.h6.dion.ne.jp/~hopiland/
1957年神戸生まれ。大学卒業、アルバイトと旅行を経て、1988年に映画『ホピの予言』によってアメリカインディアン・ホピ族の平和のメッセージと出会う。直後に初渡米し、インディアンたちによる祈りのランニング「Run for Land and Life」に参加し、北米大陸を1ヶ月間走って横断。引き続き、インディアンランナーたちを日本に招聘するプロジェクトメンバーとして、広島をスタートに核廃棄物最終処分場予定地であった北海道・幌延まで、主に原子力施設を巡って日本列島を駆け抜ける「大地といのちのために走ろう」にも参加。その後2003年3月イラク戦争開戦を契機に、ホピ族のマーチン・ゲスリスウマ氏にインタビューし、04年4月「ホピの予言2004年版」を制作する。映画上映の再開とあわせ、ワークショップも各地で開催。
岡野 弘幹(天空オーケストラ代表):第四部
http://www.tenkoo.com/okanohiroki/menu.html
1964年生まれ。1987年よりソロ音楽活動を開始。1990年ドイツのレコード会社IC DIGITと専属契約を結び、アルバムの全世界発売に至る。世界の民族楽器、自然音、デジタル・サウンドを融合し、自然界への畏敬や感謝を日本的感性で、清浄に、そして透明に表現した音楽が、ヨーロッパ・アメリカで高い評価を得る。1991年、民族楽器によるグローバルミュージック「風の楽団」に参加。1994年、天空オーケストラを結成。RAINBOW2000での細野晴臣氏(YMO)との共演をはじめ、フジロックフェスティバル、グラストンベリーフェスティバルUKなどへの出演や、熊野本宮など全国の社寺での奉納演奏なども行う。Begood cafe OSAKA 代表など活動の幅も広く、エコロジカルな文化のリーダーとしても活躍中。
■お申込み
予約優先、FAX、Eメールにて
1)氏名
2)一般/学生
3)電話、FAX(Email)
4)参加形態(希望プログラム番号・全日パスポート)
を下記までお知らせ下さい。
● 問合せ・予約申込み 應典院寺町倶楽部
TEL 06-6771-7641 FAX 06-6770-3147
E-mail info@outenin.com URL http://www.outenin.com
----------------------------------
■主催 應典院寺町倶楽部
■共催 同志社大学大学院総合政策科学研究科
■特別協力 グループ現代 おふぃす風まかせ
■協力 有限会社アンビエンス ランド・アンド・ライフ もっきん堂
----------------------------------
應典院コミュニティシネマシリーズは、コミュニティシネマ協議会のコミュニティシネマ憲章に賛同し、地域における豊かな映画環境の創造に取り組んでいます。
http://www.outenin.com/ccs/