
↑
(ダウンロードするか、iTunes for mac/winで見てください。)
言葉とビジュアルは、それぞれが互いに異なる領域を持ちながらも、そこにはメッセージが込められている。アートディレクターの徳田祐司が、前回の授業に登場されたコピーライターの小霜和也さんが提示した「言葉の威力」という主張を引用しながら、自らの主張を語った。
時間的には、逆なのだが、論旨を明確にするために、徳田さんの説明を先頭に置き、その後にピクショナリー実践の模様をお届けする。

↑
(ダウンロードするか、iTunes for mac/winで見てください。)
言葉とビジュアルは、それぞれが互いに異なる領域を持ちながらも、そこにはメッセージが込められている。アートディレクターの徳田祐司が、前回の授業に登場されたコピーライターの小霜和也さんが提示した「言葉の威力」という主張を引用しながら、自らの主張を語った。
時間的には、逆なのだが、論旨を明確にするために、徳田さんの説明を先頭に置き、その後にピクショナリー実践の模様をお届けする。

京都の公立高校で、高校の先生と一緒になって授業を作り上げている。授業では、「自己紹介」と「自己アピール」の違いをグループワークで理解するという試みをしている。前者は、自分の所属、性別、家族構成など客観的な記述をすることであり、後者は、自分の思いや目標などの自分の特徴を語ることである。この授業の目標は、「自己アピール」を作ろうということである。
ただ、こう言っても、なかなかできないものである。そこで、まず、教育実習生の一人には「自己紹介」をしてもらい、もう一人には、「自己アピール」を高校生の前で発表してもらった。二人の発表を聞いて、高校生にどこが違うのかを話し合ってもらった。結果的に、高校生は、両者の発表の相違をかなり的確に捉えていることがわかった。
次は、授業に加わった大学教員も「自己アピール」の実演をした。二名の教員が順に発表したが、ここでは私の発表(文字数として、二千字、八百字バージョンを作ったのだが、ここでは後者)だけを紹介する。
筒井洋一の自己アピール(800字バージョン)
私は、京都精華大学人文学部の教員で、インターネットや国際政治を研究しています。
みなさんに自慢したいことがあります。「自己表現力の教室」は私が書きました。文章表現や口頭表現が不得意な方に向けた書いた本です。
さらに自慢します。この本は、2000年に出版されて、4万5千部売れています。ピンと来ない方でも、一昨年と昨年に、複数の大学の入試問題が、私の本から出題されていると聞くと驚きませんか。
私は法学部出身です。そういう専門の教員が文章表現に関心を持った理由の一つは、私自身の高校時代の苦しい思い出と、もう一つは、大学生を教えた経験です。
私は高校時代には赤面症で、教壇から先生に当てられると、顔が真っ赤になって、満足いく答えができませんでした。当時は、みんなが静かにしている中で、指名されるのがとても嫌だったのです。こういう癖は大学生になるまで続きました。
もう一つは、以前北陸の国立大学にいた時の話です。大学の授業は、大規模授業が多くて苦心します。ある時、100名以上の学生に、レポートを書いてくるように言い、二週間後に提出させると、彼らは理解していました。そこで、添削して翌週返却しました。そして、二週間後にもっとレベルの高いレポートを書いてくるように、と言うと、多くのレポートはレベルが上がっていました。さらに添削して返却して、試験ではもっとレベルの高い答案を書くように言うと、さらにレベルが上がったのです。この経験を経て、私は「大学生は、適切なアドバイスを与えれば、能力は向上する」と確信しました。
これをきっかけに、1993年から、日本最初の試みとして、全学で日本語表現法の取り組みをおこないました。現在、全国の大学の三分の二の大学では同じような授業が始まっています。日本語表現法はもはや大学だけで教育されるべきではなく、高校と一緒になって取り組んでこそ効果的だと思い、本日参りました。

先日、社会メディア学科一年生必修授業「社会メディア論」で授業を担当した。この授業は、学科教員が順番に担当することになっている。私に与えられた課題は、「メディアと暴力を関連させること。」「ただし、メディアの中の暴力とというメディア論的な話はだめ。さらに、筒井の専門の国際関係論でいう国家とメディアの関係もだめ」というだめだめづくりしのお題が与えられた。加えて、「メディアの暗い面だけでなく、明るい面も言ってください」という要望もあった。
正直言って、こうした要望をすべていれた話ができるのだろうかと戸惑った。何度かアイデアを出したら、すべてボツ。「もっと明るめに」とか、「もっとメディア論的でなく」と言われて、つくづく困った。悩んだあげく、今ではもうやめてしまった、平和研究の概念である「構造的暴力」という概念を借りてきて、物理的な暴力だけでなく、目に見えない、地球的な諸問題を扱うメディアの事例にして議論した。
これはたいそう気に入られて、ようやく授業シラバスができあがった。しかし、構造的暴力を国家側から主題にした映像を探そうとすると、かなり困った。いわゆる、政府機関の広報映像なのだが、これを探すのはかなり難渋した。かつては、批判の強かったODAについても、政府は既にNGOと協力して取り組んでいるので、映像資料もNGO寄りの作品ばかり。あれこれさがしたあげく、同僚が持っていた動燃「現原子力研究開発機構」のプロトニウムは安全だ!、というキャンペーン映像が見つかった。
実は、当日まで忘れていたのだが、メディアの可能性ということで、市民メディアの映像を最後に入れる予定にしていたので、授業直前にあたふたとして、ブラジル・ポルトアレグレ市で2005年に開催された映像を最後に流して結論に持って行った。この映像は、小山師人さんが撮影された映像で、開会前の華やかなパレードの模様、ブラジル大統領の開会式での演説の他、スタンフォード大学のローレンス・レッシング教授による見事なプレゼンなど見応えのある映像だった。
ともあれ、以下に授業シラバスを転載する。映像資料などは、残念ながらアップできない。
メディアは、グローバルな暴力を助長しつつ、
われわれの未来も開く
筒井 洋一
キーワード:構造的暴力、第三世界、国家、市民、発信
1.メディアは、グローバルな暴力を助長する
日本は、平和だといわれる。この場合の平和とは、日本では「戦争がない状態」とである。しかし、日本では、戦争がなくても、いじめ、自殺、ワーキングプアなどのわれわれの身近なところでは深刻な現象が多発している。
また、日本では戦争がなくても、第三世界などでは、戦争や暴力事件が多発し、飢餓、貧困、人権侵害、疫病などが日常的におこっている。
こうした日本における社会現象や第三世界における問題を前にして、「日本は平和でよかったなあ」で済まされない。つまり、これら地球のあちこちで起こっている現象は、それぞれが別々の動きでなく、相互につながっているのである。それらは地球の各地では異なる形を取っているが、地球全体で様々な形を取っている暴力であると考えられる。こうした戦争などの物理的な暴力だけでなく、地球的な暴力を含めて、「構造的暴力」と呼ぶ。
2.メディアは、国家に奉仕する
マス・メディア
不特定多数に対して、一方向的に情報を伝える機能。それを運営するためには、技術的資金的人的なリソースが不可欠。
誰がリソースを可能にするか
社会の中の大きな組織が自己の影響力を不特定多数に与えるため
↓
国家
国家は、自らの統治を正当づけるための広報機関としてメディアを利用した
3.しかし、メディアは、市民にも広がった
近代を迎えて、市民自身が政治に本格的に関わってきたことで、市民自身もメディアを活用する必要が出てきた
フランス革命、労働運動、市民運動でのビラ
↓
市民の主張をより多くの市民に知らせたい。それによって政治的影響力を拡げたい。
↓
新聞、ラジオ、映画、演劇などを通じた政治的活動
↓
1990年代半ば以後、インターネットやビデオカメラなどの低価格化、簡便化、小型化などが市民のメディア活用が広まる
4.メディアは、われわれの未来を開くものとなった
NGO/NPO、市民の活動において、メディアによる発信は、市民やNPO/NGO 自身の活動を広める点で大きな役割を担う。
もちろん、メディアは必ずしも政治的社会的な活動にだけ関わるのではなく、われわれの日常生活を表現する手段としても役に立つ。
メディアは、当初、国家支配を正当化するために、国家による暴力を引き起こすこともあったが、市民の政治意識が高まり、またメディア機器が身近になるにしたがって、同時に暴力を防ぐ有益な道具ともなった。

著作権関係団体から連絡が来た。
昨年もある大学の入試問題に出たそうな。わずかな著作権料でもこれはうれしい。身が引き締まる思いだ。最近、徒歩での通勤を心がけているので、少しは引き締まった。
これを越える仕事をめざして頑張ろう。
感謝、感謝です。

↑
(ダウンロードするか、iTunes for mac/winで見てください。)
大学教育で食える(!)ようになったのは、1990年代末からである。「食える」というのは、一部の専門家だけが関心を持つ領域ではなく、大学業界にとどまらず、多くの関係者が注目していることを意味している。
私自身がこの業界に足を突っ込み始めたのは、90年代初めからである。当時の国立大学の教授会で、初年次教育に関する提案するとすれば、教授会になじまない議題であるとして議論さえできない時代であった。その中で、読み書き話す調べるを少人数で取り組む実習授業である言語表現科目(日本語表現法)を提案すると、激しい非難か、冷笑を浴びる時代であった。その当時私はそうした批判に対して応戦することをあえて避けてきた。その代わり、実績を積み、データを蓄積し、書面上でもまた実践上でも反論できないような取り組みをおこなってきた。
国立大学の主流の流れが変わってきたのは、1990年代末からである。おそらく大学審議会答申で個別大学の個性化が提唱された時期である。この時期を境にして、それ以前はタブーであった初年次教育や教育問題が教授会の主要議題となった。言語表現科目をあれほど非難したり、無視していた人々が、一気に教育問題を取り上げ始めた。つまり、学内行政上、初年次教育に取り組まないとまずい、という極めて打算的な判断であった。私は彼らの変わり身の早さに驚き、むしろ教授会では、あえて教育問題を語るのではなく、教育現場と他大学への啓蒙に力点を注いだ。
大学教育に関する学外での研究活動を始めたのが、1995年の大学教育学会である。個人報告で、富山大学の言語表現科目の実践とその意義について報告したら、質問が相次ぎ、終了後も多くの参加者に取り囲まれたのを覚えている。既に90年代初めから国立大学が全学で初年次教育に取り組んでいる、しかも参加者の多くの大学ではまだ科目が設置できていない状況であったので、その秘密について知りたいという参加者の意欲が溢れていた。その報告を元に、学会誌に論文を掲載した。この論文は、現在でも多分野から引用され、また話題にされている。もっとも、論文自体に学術的な新しい知見があったわけでもなく、また実証的なデータが提示されていたわけでもない。その意味で言うと、論文としてはけっしてレベルが高くない。ただ、時代の先を行っていた、あるいは無理だと思われたことが変わってきたということを感じさせる内容であった。私にとってはそうした評価を頂ける方がありがたい。
話を学外の研究活動に移す。学内での教育活動を、学内や教育活動に留めるのではなく、学外での研究活動に結びつけることで、研究者としての新しい生き方をつかみたかったのである。そこできっかけになったのが、石桁先生であった。昨日、退官講義がおこなわれたので参加した。石桁先生は、1960年代後半から情報教育を専門にされて、実践と研究を積み重ねてこられた。先生の特徴は、組織づくりと運営が巧みなことである。普通の退官講義では、自らの専門教育について一人で語る形式であるが、石桁先生の場合は違った。これまで先生が関わってこられた7つの研究会代表を順番に呼んで、ジョイントで講義を進められた。本人だけが語るのではなく、近くの人と語り合うという形式は、いかにも組織作りのうまい先生らしい企画だった。
私自身が石桁先生とお会いしたのは、1996年3月のガイダンス教育研究会の例会だったと思う。先生の本務校である大阪電通大学で開催されていた。情報教育や自然科学の専門家も交えた研究会は私にとっては初めての経験だった。ただし、研究会は手弁当で運営し、参加者全員の気持ちを高めていこうという意欲が溢れており、非常に魅力的だった。以来、今日までこの研究会で研鑽を積んでいる。写真は、研究会創設メンバー三名(左から矢内・石桁・中村先生)のスナップである。逆光だったので暗くてすいません。
私自身は、こうした先達に導かれながら歩んでいるし、これからもそうであろう。同時に、若手の優秀な専門家が本格的に登場したので、ゆっくりしているわけにはいかない。このように先達と若手に励まされながら、新しい貢献をしていきたい。

今週一週間は移動も激しいけど、面白いつながりが盛りだくさんあったが、今日は少しだけ。
名古屋で仕事をこなした後に、大学での会議を経て、夜は会津泉さんが呼びかけた集まりに参加させていただいた。会津さんの本は、1994年以後はすべて買っているので、当日献本いただけそうだったが、すべて持っていたのでもらえず、残念。スタンフォード京都センター創設者の今井賢一先生も来られていて、元気なお顔を拝見できて感激でした。私は、今頃から今井先生の歩みを追いかけているのですから、二周遅れです。
また、初対面でしたが、同姓の筒井淳也さんともお会いした。美男子であることに妬けましたが、それはともかく彼の教育に賭ける情熱、研究の一端、そして、この人は魅力のある人だというオーラを発しているのを発見して、一気に気持ちが高まりました。京都におられるので、これからじっくりと吸収しようと思います。
その他の方とも、またお会いする場面が出てきます。会津さんに感謝です。

先日、ワークショップでペアになり、互いに自分のことについて語っていた。質問項目がいろいろあったのだが、その中で「子供の頃の夢は何か?」という質問があった。私は、迷うことなく「小学時代の夢は、プロ野球選手になることでした」と答えた。
確かに小学時代の私と言えば、学校の昼休みはもちろん、放課後にも近くの京都御所のグラウンドでソフトボールを毎日していた。スポーツと言えば、野球しかなかったこともあるが、プロ野球での選手の活躍は国民を魅了したし、まさに当時の日本の躍進を象徴していた。もちろん、小学生なので硬球を使うことは恐ろしくてできず、ひたすらソフトボールだった。(たまに硬球を使ってゲームをした時に、華麗な守備でボールをさばこうと思ったら、イレギュラー・バウンドして右目にあたった。しばらく休んでまた守備をしたら、またイレギュラー・バウンドして今度は左目にあたった。それ以来、乱視になったように気がする。)
小学校では、いつもホームランを打ち、守備も外野でも内野でも起用にこなせたので、得意満面だった。近所のお母さんが家に来て、「**君は、将来、本当に**(球団名)に入ったらいい」と言っているのを聞いて、本当にその気になったものだ。小学生の時には、プロ野球選手になることが夢だったし、それを実現しようと思っていた。
だが、たぶん五年生頃から、サッカーに興味が出たり、水泳も得意だったりして、夢がぐらついてきた。中学校では水泳部に入って、それなりに活躍したのだが、将来の夢ではなかった。高校時代に体調を壊してスポーツをあきらめ、受験戦争を経て、大学へ。その後、大学院へと過ごしてきた。
ワークショップの話に戻す。つまり、子供の頃の夢を思い出していると、小学校の夢ははっきりしていたが、中学、高校、大学、大学院時代には夢がなかったことがその時にはっきりわかった。道理でこの時代は、気持ちが落ち着かないというか、目標を失っている気がしていた。人生を投げていたのかもしれない。
でも、30歳代半ばになって、人生が楽しくなってきた。その気持ちはいまでも続いているし、途絶えることもないだろう。遅咲きながらも人生を楽しめるようになってきたのだが、それは夢を持っているからである。
では、それは何かというと、誰か他の人が目標ではなく、自分自身が目標となっている。もちろん、現在の自分自身ではなく、5年あるいは10年後の自分が目標である。今の自分とはどこまで違っているだろうか。それを目標にしながら、生きていきたい。ますまず楽しみになってきた。

↑
(ダウンロードするか、iTunes for mac/winで見てください。)
連休最初の29日に大阪市内に出かけたが、普段は人出溢れている、心斎橋周辺でも極端に人出が少なかった。きっと地元の人も観光客も天気がいいので、郊外に足が向いているのだろう。店が休みが多かったのは残念だが、車も人も少なくて、ゆったりと回れた。
大阪・上町台地の調査第二フェーズも最終イベントを迎えた。夕方から最終イベントがあるので、昼からゆっくりと上町台地を歩いた。心斎橋から、長堀通りを東進し、空堀商店街、萌・練・想の町家から南進して、寺町の寺院街からさらに南進して、四天王寺へと行った。そして、今度は北上して上本町駅から、東進して鶴橋で夕食を食べてから、北東へ進み、イベント会場のNEXT21まで歩いた。約5時間の探訪であったが、それぞれの場所は歴史を感じさせるためにまったく疲れを感じなかった。
ただ、上町台地のほとんどを歩いて見て、コンテンツの深みにもかかわらず、それが生かし切れていない実態に遭遇して、むしろ問題点を痛感した。具体的には、
などである。
せっかくのコンテンツを十分に生かし切れていないことをどう改善するのかが今後の課題であろう。
夕方のイベントについて。
「上町台地まつり絵巻」クロージング・イベント“上町台地のまつりを紐解く”スペシャル・トーク、と題した企画は、連休中にもかかわらず、会場が一杯になるほどの60名程度の参加があり、大変盛況であった。こつこつと積み上げてきた活動が徐々に浸透していることがわかる。
ゲストは、澤井浩一(大阪歴史博物館学芸員)と北川 央(大阪城天守閣研究副主幹)さんであった。その中で特に面白かったのは、西国三十三カ所や四国八十八カ所という巡礼が、都市生活者にとって体験しやすい方法として、国単位、郡単位、さらには都市単位へと徐々に範囲が狭まり、ついには浄土宗優勢の大阪では円光大師(法然上人)二十五カ所という上人個人をたどる巡礼までに狭められ、それがやがて他の都市へも波及していくきっかけとなったということである。都市生活が繁栄した大阪から新たな祈りの習慣が生まれたのであった。
議論の最後に、北川さんが、今後の「まつり」とは、変わらない神事としての祭礼と、新しさを求めるイベントとを含んだものととらえるべきであるという提言されたことは、貴重なコンテンツと変わりゆく社会との接点を模索する必要性を訴えたものであった。
最初の映像は、トーク終了後の懇親会の締めで、「上町台地から町を考える会」代表であり、應典院住職秋田さんの五本締めである。そろそろやめたいと言いながらも、やると決めたら、背広を脱いで、全力で取り組む姿が彼らしい。
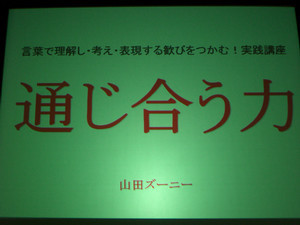
昨日、京都精華大学でコミュニケーション・インストラクターの山田ズーニーさんのワークショップがあった。精華大学で三年前から実施されている「日本語リテラシー科目」が文部科学省の特色GPプロジェクトに採択されたことを記念して開催された連続企画の一つであった。詳しくは、プログラムを見ていただくとして、私が山田さんの回に行こうと思ったのは、この時が唯一ワークショップで実施されたからだ。
それとは別に、現在のブログの先駆者である糸井重里さんに注目しているので、そのつながりから山田さんのワークショップには是非体験したいと思っていた。ワークショップのインストラクターというと、受け答えがはっきりしていて、スポーティーな衣装を軽快に着こなしててきぱきと仕事するタイプが多い。山田さんの場合、もちろん話はわかりやすいのだが、声が特にいいわけでもなく、また、どちらというとあまり動きのない方である。桃井かおりさんと似ているかも。
独立以前は、ベネッセの高校生向け小論文の添削を長年されていたので、文字との対話は得意でも、人前で話すことは苦手なタイプだったと思う。でも、その苦労を一生懸命自分の糧とされたようだ。そして、現在では、単なる講演ではなく、ワークショップで人との対話を拡げる分野に入って行き、個性的な形式を作り上げられたのだ。ワークショップの中身については、他の場所で参加された方が報告されているので、それとよく似ているので参照してほしい。
実は、私は、今度700名規模の学生を相手に授業をする機会がある。わずか90分間のうちの60分間が私の持ち時間だが、普通ならば私の話だけで精一杯の時間である。それを承知でわざわざ一つワークを入れようと思う。それがどれだけ私の話を体験させるものになるかどうかが試されるが、昨日の山田さんのワークショップからかなり示唆をいただいた。ただそれをまねるのではなく、自分なりの個性が発揮された内容にしてみたい。
ふだんは、知り合いと何気なくしゃべっている。短時間だとほとんど疲れない。逆に、国際問題の行方や児童殺害などの深刻な話題について話しているとかなり疲れる。でも、その疲れは、どちらかというと集中的に頭脳を使ったために、頭だけの疲れを感じる。
誰かと話している時に、気楽なおしゃべりをするか、頭の疲れを感じる重い話題を話す以外の対話の仕方はないのだろうか。
私はあると思う。それは、ワークショップやファシリテーションの中で、年代、性別、職業の異なる初対面の人とワークをする時だと思う。数時間のワークが終わったときの疲労感は、ふだん経験しないタイプである。つまり、主として対話だけで進むワークであっても、頭が疲れるだけでなく、体中の筋肉が疲れる。たとえば、60分間のインタビュー・ワークをすると、体はほてるし、頭は熱くなっているし、なにかふだん使わない頭脳や筋肉を使っている気がする。私は、それを「心の筋肉痛」と呼んでいる。
心の筋肉痛は、動きたくなくなるほどの疲労の中にも、爽快感がある。でも、こういう不思議な疲労感は、一晩すると取れている。疲労感が取れた後には、頭が異常に働くようになる。アイデアが出る。ふだんいかに自分が大した仕事しかしていないのかと思うくらいだ。ワークショップやファシリテーションの体験は、その気持ちを日常生活にフィードバックさせる不思議な道具だと思う。その秘密をさぐるのが、ここ数年の私の研究テーマになる。

毎年一、二回、出版社から増刷の連絡が来る。ある時は5千部、ある時は15百部と変動はあるが、2000年発売以来コンスタントに増刷を重ねている。今年はどうかなと思いながら四月を迎えた。
今朝、郵便ボックスを見たら、版元からの郵便小包が入っていた。そこには「15刷、*000部」増刷と書かれてあった。前回よりも冊数が増えている。7年目に入っても増刷できたことには読者に対して感謝にたえません。しかも、ついに4万5千部を越えた。14刷の時にも書いたが、この本を担当した編集者が退職して、改訂版が出せていない。最近経験を積んできたファシリテーションと***を加えた新企画で再出発できたらと思う。
ともあれ、まずはうれしさを表現することができたことに感謝です。