
昨日、自宅から京都駅まで徒歩で歩いた。大阪に用事があったので、どこまで歩けるかと思いながら、2時間前に自宅を出た。結果は、1時間40分で歩けた。町並みを見ながら、途中で知り合いに会いながらの行程だったので、比較的スムーズだった。
京都駅まで行ったのは、大阪の「上町台地からまちを考える会」が中心になって取り組んでいる現地調査の報告会を聞くためだった。大阪ガスエネルギー・文化研究所と京大大学院高田・神吉研究室、同志社大大学院新川研究室、大阪市大大学院三浦研究室が共同して取り組み、都心居住支援のための調査をおこなった。この調査は日本社会の少子高齢化が進行する中で、都市生活の意味を探る長期的な視野をさぐるものである。上町台地は、大阪市の中心部に位置し、大阪城、難波宮跡などの遺跡の他、大学や学校が集中している閑静な文教住宅地である。恵まれた住宅地を調査することは、短期的な施策ではなく、より長期的な都市生活のトレンドを把握することになる、という三浦研さんの説明は面白かった。
今回の調査を中心になって担当した京大の院生がかれらの修士論文の報告を兼ねて発表した。報告会場は、大阪ガスの実験住宅であるNEXT21内の会議室であった。80名入れば一杯の会場に60名以上が押し寄せ、院生たちの報告に聞き入った。参加者は、研究会メンバーの「考える会」や大学関係者はもちろんだが、アンケート調査や文化行政で関係した大阪市職員、システム開発に協力した株式会社縁人スタッフ、懇親会の料理を提供してくれたメンバー、そしてアンケート調査に協力してくれた地元の方など年代も職種も異なる人々であった。
こういう多彩な人々の前で、院生が報告するというのは滅多にない。現地調査で地域にお世話になり、そこで得た学問の成果を地域に返すという、当たり前のことだが、なかなか得られない機会だった。こうした光景を私も大学で実現したいと思っているし、その第一歩を踏み出そうとしている。大きな目標を最初に掲げ、それに熱中する経験はかけがえのないことだと思う。










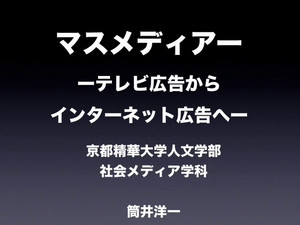

![不都合な真実 スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD] 不都合な真実 スペシャル・コレクターズ・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51U8zOoRMyL._SL160_.jpg)
