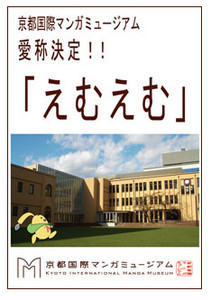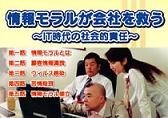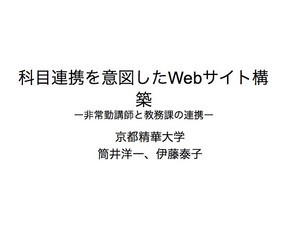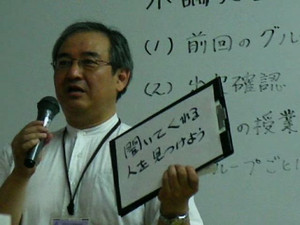パネリストの一人の杉井鏡生さんは、十年以上前に富山大にいた時にお会いしたことがある。私の敬愛する桂木健次先生を訪ねて来られた時にお会いしたのだった。確かあの時には、学内でのネットワーカー同士のやりとりがいろいろとこじれて、その場面に杉井さんも関わることになったように記憶している。
大学でも企業でも、情報モラルについては近年非常に厳しくなってきた。その厳しさは、ユーザの正当な利用を妨げることであってはならないと思うが、この分野の最先端の話を聞いて刺激を受けようと思う。私も行くつもりですので、皆さんも是非おいでください。
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
■■■■ 平成19年度情報モラル啓発セミナー in 京都 ■■■■
【情報社会で企業に求められる情報モラル】
■■■■人権に配慮した個人情報の保護・情報セキュリティ■■■■■
セミナーの情報 http://www.hyper.or.jp/moral2007/kyoto/
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
本セミナーでは、情報社会において企業がより高い信頼を獲得し、より効
果的に活動するために必要な考え方や取り組みについてご紹介いたします。
ビジネスでITを活用する際に必須の内容です。是非ご参加ください。
【概要】
◇日 時:平成19年7月13日(金)13時00分〜17時00分
◇対 象:中小企業の経営者・管理者、実務担当者、企業でインターネットを活用する人等
◇定 員:200名(先着順・定員になり次第締め切ります)
◇参加料:無 料
◇場 所:京都リサーチパーク(西地区4号館バズホール)
京都市下京区中堂寺南町134番地 JR「丹波口」駅下車徒歩5分
(駐車場有・4時間分の無料駐車券を、受付にて配布しておりますので、
お気軽にお声掛けください。台数に限りがございますことを予めご了承ください)
http://www.krp.co.jp/kaigi/
◇主 催:中小企業庁、近畿経済産業局、(財)ハイパーネットワーク社会研究所
◇後 援:京都府、京都市、(財)京都産業21、(財)京都市中小企業支援センター、
京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、
(財)関西情報・産業活性化センター、(財)ひょうご産業活性化センター、
(財)奈良県中小企業支援センター・(独)情報処理推進機構、
日本ネットワークセキュリティ協会・(社)日本青年会議所・CANフォーラム
(財)日本情報処理開発協会 ほかを予定
【プログラム】
◇主催者挨拶 13:00〜
◇ビデオプレゼンテーション 13:15〜14:00
「情報モラルが会社を救う―IT時代の社会的責任」
財団法人ハイパーネットワーク社会研究所 会津泉・杉井鏡生・渡辺律子
・IT化を進める中小企業が個人情報漏洩などのトラブルに遭遇し、社長・社員が奮闘する様子を題材にした啓発ビデオを上映し、社
内教育への活用法などを解説します。
◇講演 14:00〜15:00
「個人情報保護に対する企業の実践的なの取り組み」
ネットワンシステムズ株式会社 情報セキュリティセンター長 山崎 文明
・企業が個人情報の管理を徹底するための効果的な方法、情報セキュリティの
具体的な対策など。
◇講演 15:15〜16:15
「ウイルス・スパム・Winnyなどへの対策-企業の信頼確保のために」
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)研究員 加賀谷 伸一郎
・ウイルスやスパイウェア、Winnyなどによる情報漏洩は、人権問題にも関わること。
具体的な被害事例、具体的な対策方法など。
◇パネル討論 16:15:〜17:00
「いまなぜ情報モラルなのか」
・山崎文明、加賀谷伸一郎、杉井鏡生 モデレータ:会津泉
会場との質疑を交えて、パネル討論形式で討論する。
※参加された方には、教材として使用する情報モラルの取り組み方を題材にした啓発用ビデオとパンフレットを無料進呈します!
【セミナー参加申し込み方法】
次の㈰から㈯の項目について、メール(kyoto-sanka@hyper.or.jp)
またはFAX(097-537-8820)でお送り下さい。
記載事項㈰件名:「 からの紹介」とご記入ください。
㈪会社名 ㈫所属・役職 ㈬氏名 ㈭住所 ㈮電子メールアドレス
㈯電話番号・FAX
◆お問い合せ先◆
(財)ハイパーネットワーク社会研究所 担当:渡辺・倉掛・植木
電話番号:097-537-8180 FAX番号:097-537-8820
Eメール:moral@hyper.or.jp