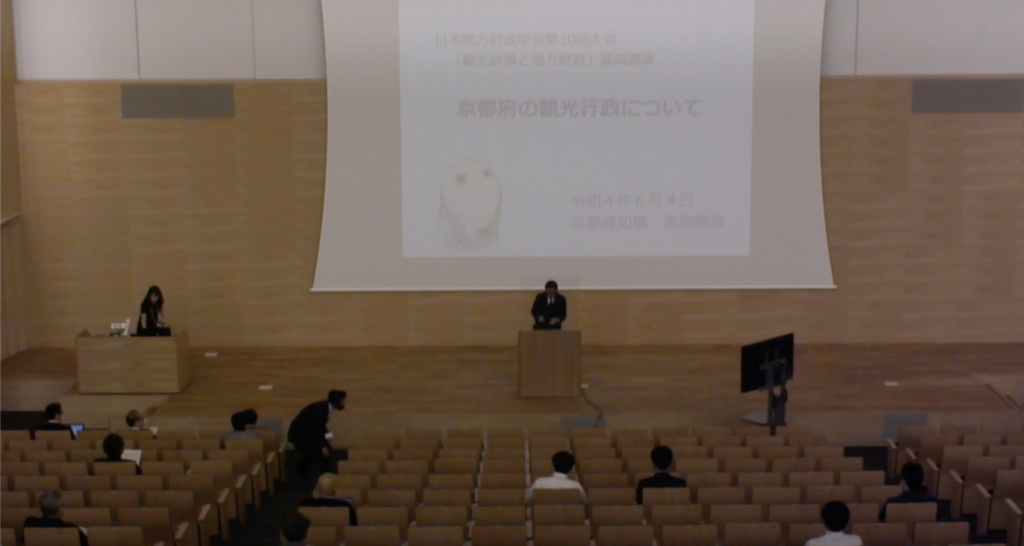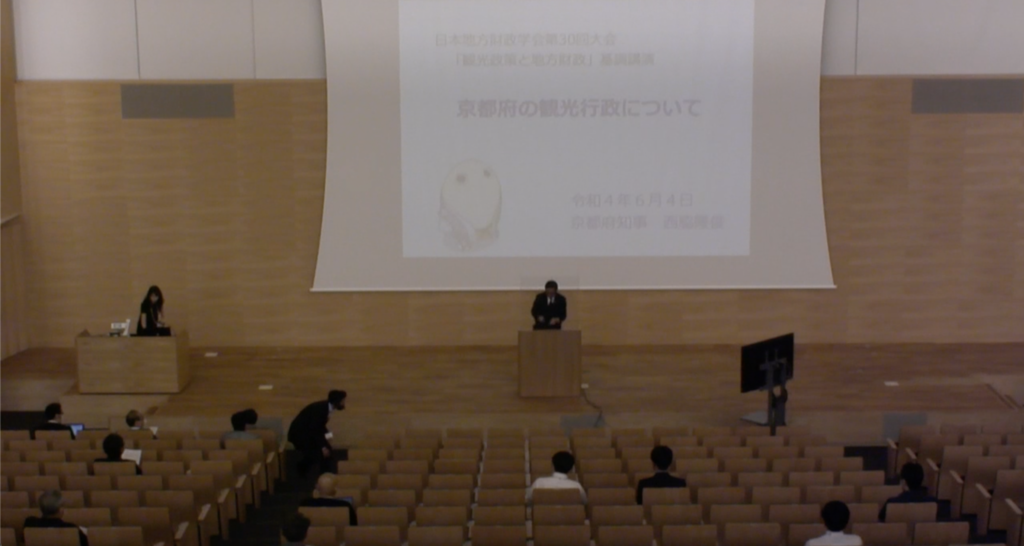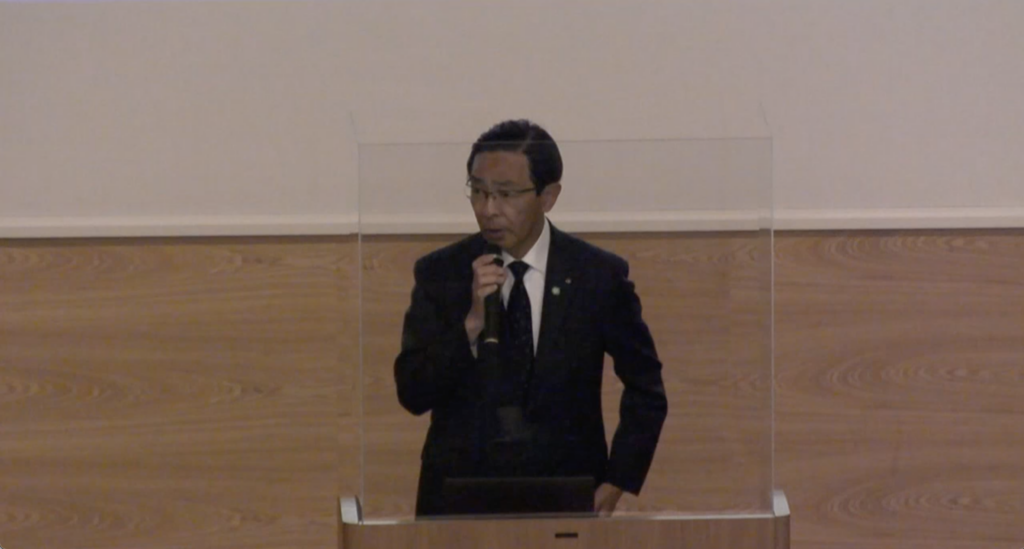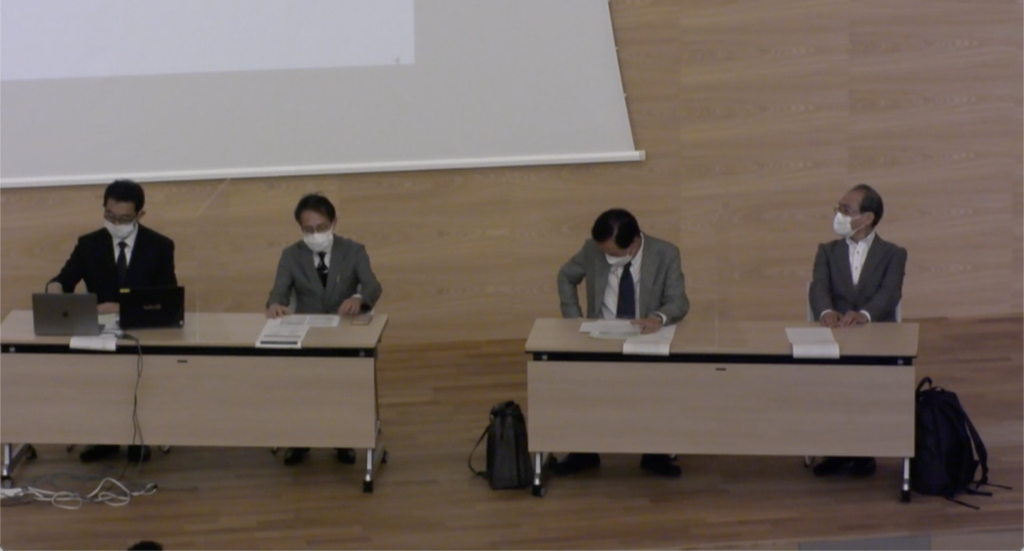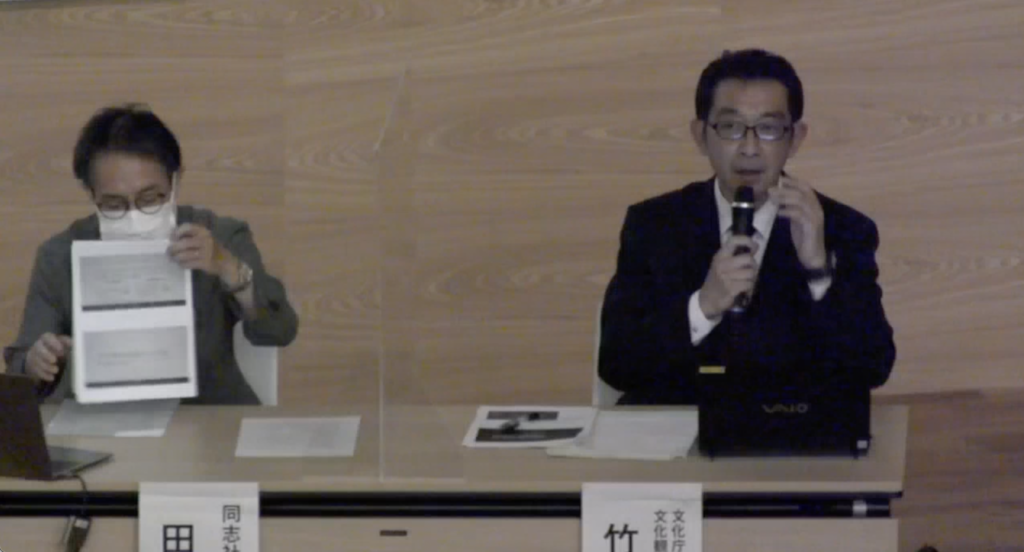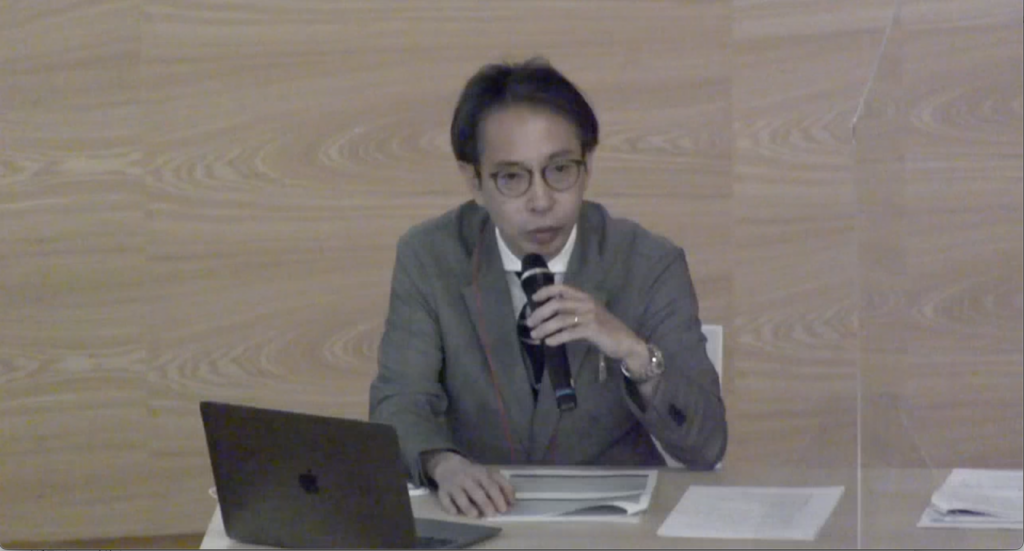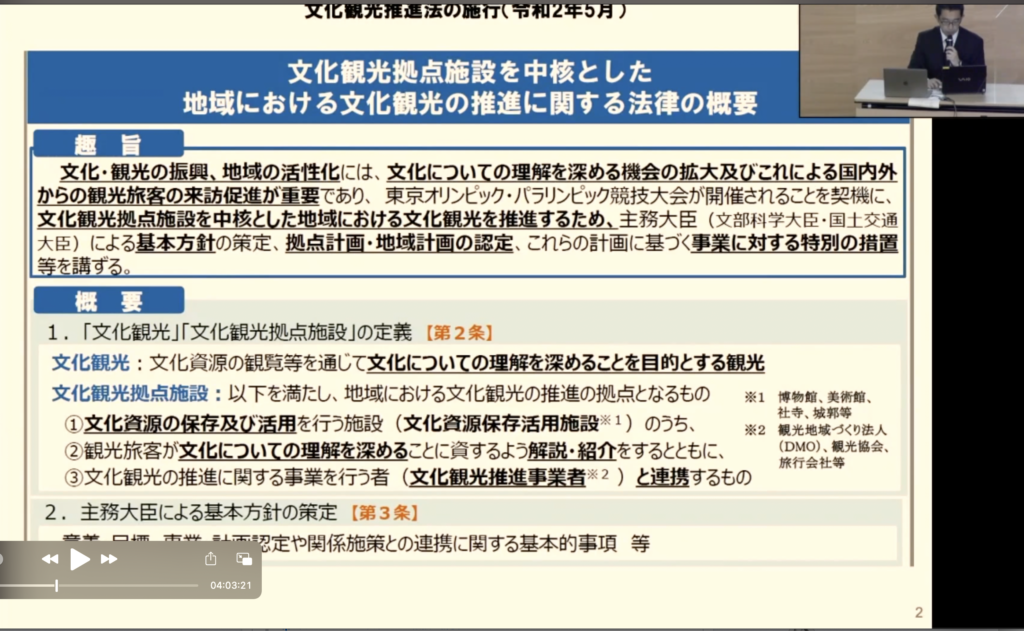「医者の仕事は、医者が何かをするのではなく、人間の体の邪魔をしないことだ」
医者が以上のようなことを言っていたのがとても心に残っている。
一般に、医者は患者の病気やけがを治すために全力を注ぐと思われているが、むしろ、医者は病気やけがに対して謙虚になる必要があることを教えている。
実は、私は、教師も同じだと思います。
でも、実際の授業では、
教師が頑張れば頑張るほど、学生や生徒の意欲ややる気が伸びる、
と言われます。
もちろん、頑張った学生や生徒は偉いと思いますし、それを見ている教師はさらにうれしい。でも、これは、教師が頑張らないと、学生が伸びないと言っているのと同じです。
もちろん、教師がいなくても頑張る学生もいますが、いずれにしても教師は頑張らないと行けない、
を前提にしているのがおかしい。
頑張った姿を見せないと同僚や上司の反応がよくないし、まずは、自分がそうでないといけないという思い込みが強いです。
しかし、Jリーグ・サッカーコーチは、コーチ自身よりも、選手が自分で努力するように持って行きます。
一番いいのは、
教師が頑張らなくても、学生が自分で頑張っていくこと
ですし、それを授業の現場で可能にするのが教師の仕事です。
私の場合、いくつかのルールを決めておいて可能にしています。
1.授業では、教師が担当する時間を事前に決めておきます。
私は、90分授業中10分間が私の持ち時間です。
担当時間を事前に決めて、そこに全力を注ぎます。
2.可能な限り、授業は一人ではしません。オンライン授業の場合
には、必ず複数で担当します。
10月からの授業は、授業ボランティアの方と一緒にしま
す。彼らが授業の進行を担当して、私は、それ以外の仕事をし
ます。オンライン授業になると、テクニカルサポートをしま
す。
3.毎回の授業設計は、できるだけコンパクトにして、突発的かつ
重要なことが起きれば、いつでも授業内容を変えます。
事前に授業内容は決めておきますが、
突然必要なことが生まれた場合に、実現するための余裕を持
っておきます。
以上のようなルールを決めておくことで、自分のやるべきことが明確になります。
10月からの授業には、
実力のあるボランティアばかりが集まってこられるのでありがたい限りですが、他のボランティアと確認が取れている限り、15回全回参加はしなくても困らないように
余裕を持たせています。
一人の教師が授業時間全力で頑張ると、本人にとっての充実感がありますが、本来、最大の恩恵を得るべき学生や生徒は教師の頑張りに応じた頑張りしかしないとすれば、それはまずいことです。
むしろ、授業終了後に、教師がいなくても、学生・生徒自身で学び出せば、それは教師にとって最大のやりがいになります。
今年の授業をどのように準備するのかは、集まったボランティアの中で話し合いながら決めていきます。
現在既に何名かのボランティアが名乗り上げてくれていますが、
8月末までボランチは募集しますので、早めにお知らせ下さい。
詳細は、以下をご覧下さい。
【京都の大学の授業を一緒に創りませんか? 9年目の挑戦です!】
https://tsutsui-media.net/?fbclid=IwAR0e16V44hkRFixZvInVtISHhhYmWMsnrNPxf8KVf4uW_DyzuSdRf6I4K5g