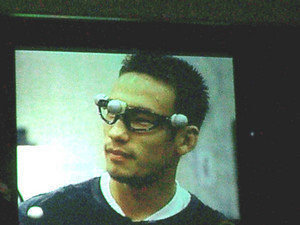日本語表現法に取り組んでから10年以上経つ。その中ではいろいろの方に出会い、面白い実践をされていることに感銘を受けた。その中で、口語表現法の師匠に荒木晶子さんがいる。彼女は、15年前に桜美林大学に教員になって以来、口語表現法の実践に手探りで取り組んでこられてきた。
私も1991年に彼女の講義を聴講させていただいた。普通の、というと失礼だけど、日本人の教員に講義を聴講させてくださいというのはなかなか言いにくい。実は私もあまり好きでない。しかし、彼女は「どうぞいらしてください」と快諾していただいた。
講義内容は、あらかじめ考えてきた一分間スピーチを学生が順番に前で話す。それ以外の学生はそれをコメントカードの項目に従って評価する。スピーチの間に、荒木さんが数十秒間ビデオで録画している。これを受講生全員が実践する。終了後、収録したビデオを見て、受講生の進捗状況を自ら確かめる。自身のスピーチを録音しているので、次回までにテープ起こしして、自分のくせを知るという手順である。
こうした実践も15年間改善を繰り返し、また学内外での評価も上がっているため、非常勤講師の方にも協力してもらっている。その共通テキストとワークブックが先日出版された。
今年後期に他大学で講義があるので、もう少し早かったらテキストとして使用させていただいたのだが、残念。
受講者としても、また講義者としても、双方の立場から使用できるこの書籍はおすすめです。

自己表現の技法―文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション (専門基礎ライブラリー)
- 作者: 畑山浩昭,荒木晶子,尾関桂子,為田英一郎,穐田照子
- 出版社/メーカー: 実教出版
- 発売日: 2003/12
- メディア: 単行本