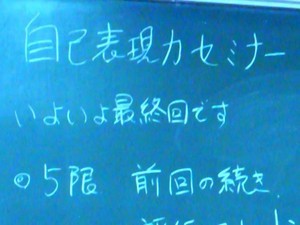月曜日に、大阪・ガスビルの大ホールで、
『地域を活かすつながりのデザイン』出版記念イベントが開催された。私も執筆者の一人として、午後の出版記念セッション「地域資源から発想するコミュニティ・デザイン」に参加した。
まちづくりのイベントだからといっても、実は170名もの申込者があり、当日、インフルエンザの影響で若干減ったが、それでも160名程度の参加者が集まった。13名の執筆者全員も奇跡的に集まった。参加者の類型も実に多彩で、大学、近畿の行政、企業、団体、主催者の大阪ガス関係者などがホール一杯に集まった。
記念セッションは、主な執筆者がそれぞれ自分の論文論旨を中心に、その学問的な位置づけをしながら話し、三時間半の間、本を読まない人でもほぼ概要がわかるほど懇切丁寧な発表であった。
終了後、基調講演を担当された新川先生(同志社大学)とお話ししていたら、大阪のまちづくり活動で言うと、上町台地がダントツに抜きんでているとのこと。もちろん、地域活動としては、もっと密度の濃い事例はあるのだが、外部への発進力や影響力では他を寄せ付けない勢いがある。
その原因の最たるものは、これに関わる地域の人や外部から関わる人たちの人的大きさと人脈が上げられるだろう。僧侶、建築家、地域の観光仕掛け人、在日団体幹部、まちづくりプロデューサ、研究者など実に多彩な人材が楽しみながら取り組んでいる。
かつて地域活動といえば、地域ボスが特権的な立場であったが、上町台地の場合、対話型のリーダや支援者などが中心を担っているのが特徴だ。こうした人たちが今後の地域とまちづくりを担っていくのだろう。私は、部分的にしか関われていないが、それでも彼らと出会うことは、新しい刺激を得られるチャンスである。執筆者全員の参加を目指して、事務局担当者からの熱烈な呼びかけが効を奏し、予定が入っていた私も予定が取りやめになって参加できるようになった。彼らの足を引っ張らなくてよかったと思う以上に、彼らの側にいられた幸運をかみしめていた。
われわれの成果の一端を是非ご購読ください。