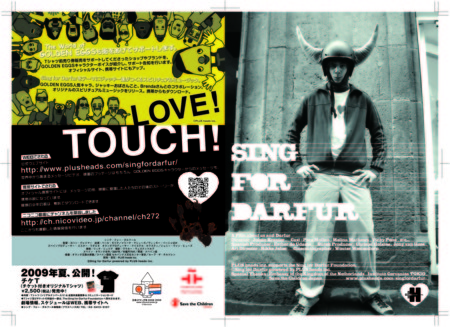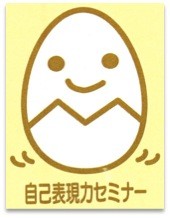我が大学では、今年度から画期的な授業公開を実施している。
学生が日々接する教育の現場と言えば、授業である。授業を受けた学生はその内容を知ることがで
きるが、それ以外の人には知ることができない。かねてから、これをなんとか表に出したいと思っていた。
そこで、どうすればうまくいくのかについて授業公開の方法を検討してみた。
一つは、実際の授業を公開して、それを参観する伝統的な方法である。もう一つは、e-learningによる最先端の方法である。マサチューセッツ工科大学(MIT)のオープンコースウエア(OCW)のように、有名大学の有名教授の授業が無料でネットで公開されれば、内容はともかくとして、授業公開されるだけでも意味があるだろう。
ただ、私自身は、もう少し別の次元で授業公開を考えている。普通の教育現場で、きらめきを感じる授業に出会うチャンスを増やすことである。しかも、この授業公開では、これまであくまでも見られる側、記録される側に過ぎなかった学生学生自身に授業記録を公開してもらうようにしている。
その試みは、既に私が非常勤講師と一緒に担当している授業「クリエイティブの可能性」では、おこなっている。ただ、ここでの記録作業は、クオリティーが高いため、どうしても文章力のある学生に記録者が偏りがちである。
そこで、もっと気楽に記録できるすべはないかと検討を重ねた。そこで、学生の参加が求められ、かつ授業プロセスを見せる実技系の授業を対象とすることに決めた。担当教員を通じて、受講生の何名かに広報担当者になってもらい、かれらが授業風景を撮影したり、文字化したりするのである。もっとも、広報担当者であっても、受講生であるので、授業に専念できる程度の仕事量にする必要がある。
従来は、担当教員や学生に負担をかけ過ぎたのであり、長続きすることが少なかった。そこで、今回は、教務課職員や教育支援職員と一体になって、広報担当者の作業を支援する態勢を整えた。既に公開が始まっている授業を含めて20科目程度の授業を一挙に公開している。
科目名は、
【農的くらし】【編集技法】【広告表現技法】【ノンフィクション・ルポルタージュ】【クリエイティブの可能性】 写真表現技法】【言語表現技法】【社会調査技法】【シナリオ技法】【メディア・システム設計】【メディア・データ編集】【シナリオ技法】【プレゼンテーション技法】【クリエイティブの可能性】
などである。
このプロジェクトの特徴は、
1.約20科目同時にブログサイトを立ち上げたこと。
2.投稿者は、授業の受講生から選ばれた広報担当者がおこなっていること。
3.毎回の授業の流れ、授業風景、授業に対する感想などが書き込まれていること。
4.学生を支援するために、教務課から委任されたスタッフが配置されていること。
5.全授業の公開動向を4.のスタッフがフォローしていること
である。
このように大規模な授業公開の試みは、
精華大学では初めての試みであり、
全国的にも先進的な活動である。
以下のサイトからリンクをたどってほしい。
「京都精華大学人文学部ワークショップ科目」
それらは、みなさんにとっても、きっと「きらめきを感じる授業に出会うチャンス」を提供してくれることと思う。
追記:
このプロジェクトを実践しているのは、教務課職員藤井剛さんと、教育支援スタッフの徳日俊聡さんです。