
先週金曜日に、宗田勝也さんにPodcastingの操作方法をお教えしたら、たいそう意欲をお持ちになった。教えている側としては、予想以上に喜んで頂いたことは光栄なことである。しかし、それ以上にうれしかったことがあった。昨日、宗田さんから、Podcastingのサイトをさっそく立ち上げた、という連絡を受けたことである。
ジングルあり、BGMありで、番組担当者らしく構成がしっかりしている。今後のご活躍をお祈りしています。
「難民ナウ!」ポッドキャスト版

先週金曜日に、宗田勝也さんにPodcastingの操作方法をお教えしたら、たいそう意欲をお持ちになった。教えている側としては、予想以上に喜んで頂いたことは光栄なことである。しかし、それ以上にうれしかったことがあった。昨日、宗田さんから、Podcastingのサイトをさっそく立ち上げた、という連絡を受けたことである。
ジングルあり、BGMありで、番組担当者らしく構成がしっかりしている。今後のご活躍をお祈りしています。
「難民ナウ!」ポッドキャスト版

今朝、職場の郵便ボックスを見たら、ある団体の封筒が投函されていた。その団体は、ある検定試験を実施している。
同封資料を見ると、見たことのある本の表紙(『自己表現力の教室』)のコピーなどが入っていた。添え状を読むと、先日の検定試験に、上記の本の一節(筒井担当分)が検定試験問題として出題されたとの連絡である。出題部分を読むと確かに私の文章だ。文章題なので、この文章から枝問が出題されている。問題の主旨は、きっちり著者の意図をくんでいると思う。
著者としてこうして入試や検定試験に出題されるのは名誉なことだ。今回の場合は、商業目的ではないので、謝金はでないが、出題されること自体で十分満足である。昨年度の入試問題にも出題されたことは既に書いたので、今回で二度目である。もちろん、文章を細かく見ていくと、冷や汗部分もあるのは事実だ。しかし、なんとか大した誤りにならない程度なので、出題者も許容範囲だと認定したのであろう。
1990年代初めから言語表現科目を提案して、実践した当初は、私の文章や発言の拙さを会議の場でよく揶揄されたものだ。それを聞いたときには、私の心の中では、「私の稚拙さを指摘するあなたはどうなのか?」と発していたが、口に出さなかった。感情をぶつける代わりに、私は別の方法をとった。つまり、その場での反論ではなく、時間はかかっても少しずつ成果を積み上げていこう。成果の蓄積によって反論の代わりにしようと。
自己満足も含めて言うと、文章に関してはいくらかましになったし、それ以上にまとめるのが早くなった。これははるかに進歩している。ただ、口頭表現に関してはいまだに発展途上である。日本語表現法を教えている時にもこの点の負い目はある。
しかし、最近、ポッドキャスティングを初めて、ゲストに対するインタビューをする必要に迫られている。自分の声を後で聞くので、その稚拙さがよく分かる。わかるからこそ少しずつ改善する必要性が沸いてくる。いずれにしても、他人の目に触れることで、自分の改善につながるのであれば、自分にプラスになる。そのことが次のきっかけとなればいいのである。

私の知り合いの中で、ポッドキャスティングを始めそうな人が増えている。
昨日は、宗田勝也さんにお会いした。彼は、京都三条ラジオカフェにおいて、世界唯一の難民問題を発信する番組担当者http://radiocafe.jp/b_syoukai/nanmin_now.php?id=nanmin_nowである。彼に、ポッドキャスティングの説明をしたらたいそう興味を持たれた。ラジオ番組ではともかくとして、それ以外ですぐにでも始めそうな喜びようだった(学生に説明する場合には、音声の保存形式がどうだとか、ファイルの変換とかの説明すると、それを理解するので精一杯だ。しかし、宗田さんの場合には、その説明をすぐに理解されて、どういうコンテンツを作ろうかと思いめぐらされているのがわかったので、説明しがいがあった。やはりコンテンツを発信している人は感度がいい。)
今日、ジャーナリストの岩本太郎さんのブログを読んでいたら、Jストリームさんhttp://www.stream.co.jp/の支援を受けて、三ヶ月間週二回のペースで発信されるそうだ。テーマは自由ということなので、よけいに楽しみだ。岩本さんのことだから、メディア話だけでなく、占いや自動販売機など何でも来いだろう。そういう柔軟なところが男性に限らず、女性にも人気のあるゆえんだと思う。
Jストリームみたいな企業の支援を受けられるのはうらやましいなと思いつつも、なにはもとあれ、まず自分自身の試みが次を開くと信じて挑戦し続けよう。(おじさんがこういう新しいチャレンジに積極的でありながら、ゼミ生や学生の動きが本当に遅いのはどうしてなんだろう。)
今月26〜27日神戸長田のFMわぃわぃ10周年記念イベントhttp://www.tcc117.org/fmyy/forum01/index.htmlの情報発信の一環として、私とゼミ生がポッドキャスティングを担当することにした。
山江村の時よりも、聞きやすく、わかりやすく、現場の雰囲気を伝えるように工夫をしようと思う。
具体的には、岩本さんのブログにもコメントしたが、
ことを考えています。
マスメディアとも、ストリーミングとも違った、コンテンツや臨場感をどう出すのかが重要だ。
ところで、「けろろぐ」学術部門でのランキングも一時的に二位になったが、他部門から参入してきた強敵が圧倒的な強さで一位に躍りでて、現在三位。でも、かつての一位だった二位のサイトを抜くのはもう少しだ。一位を目指すためには、さらなる工夫が必要だし、いい強敵が現れたと思う。
誰か一緒にしませんか?
神保哲生さんの講演をダウンロードする。
今夜は、京都三条ラジオカフェに素晴らしいゲストが来られた。わが国のビデオ・ジャーナリストの先駆者である神保哲生さんだ。
神保さんが1999年から主催されているニュースサイト「ビデオ・ニュース・ドットコムhttp://www.videonews.com/」では、神保さんと社会学者の宮台真治さんがキャスターとなって、毎回違ったゲストを迎えた番組を放映している。
そこでは、マスメディアでは取り上げないけれども、重要な社会課題や、逆にマスメディアの特ダネより、はるか前から取り上げている超特ダネもある。
その神保さんご本人が、ジャーナリズムとは、市民メディアとは、現在のマスメディアの抱える構造的な問題などを熱っぽく語った。おそらく、ラジオカフェでは、ここまで正面切ってジャーナリズム論をテーマにしたことはなかったのではないか。なお、講演内容の発信に関しては、事前に神保さんから承諾していただいている。
講演後おこなわれた、参加者との質疑応答もかなり真に迫った内容であるが、都合により割愛する。それでは、お聞き下さい。
なお、ビデオ・ニュース・ドットコムhttp://www.videonews.com/」のニュースは視聴可能だが、月500円の会費を払えば全編見ることができる。

Tsutsui-Pod-Mediaでは、ついに1000アクセスを達成した。
http://www.voiceblog.jp/tsutsui/
「けろろぐ」学術部門では4位となったが、3〜5位の争いが激しい。いや、3,4位の争いだ。私が追い越せる仕掛けを考える必要がある。
今夜は、ある映画の招待試写会に行ってきます。映画の原作者、監督、俳優さんなどのインタビューが取れれば、アップする。
私のコンテンツの配信方法はだいたい決まってきた。
だ。
上記のスタイルだと私自身が動かないとコンテンツが増えないので、行動しない、できない時には苦しい。しかし、スタジオ録音よりは、はるかにライブ録音の方が面白い。インタビューも録音技術も素人だが、しばらく繰り返すことで上達できるだろう。
自分のスタイルが確実にできあがったところで、また次の展開を考えよう。

![カーテンコールメイキング 佐々部清監督と昭和ニッポンキネマ [DVD] カーテンコールメイキング 佐々部清監督と昭和ニッポンキネマ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/3170G1K8WGL._SL160_.jpg)
カーテンコールメイキング 佐々部清監督と昭和ニッポンキネマ [DVD]
この映画の原案を三十年くらい前に書いた大阪・應典院主幹(住職のこと)の秋田光彦さんから招待チケットをいただいた。それで喜んで見に行った。
大阪・リサイタルホールの会場一杯に入った観客を前にして、『半落ち』で有名な佐々部清監督、主演の伊藤歩、共演の奥貫薫、井上尭之さんが舞台挨拶に来られていた。
舞台挨拶を勝手に撮影していいのかどうかわからなかったので、受付の方に聞いたら、記者証をくれたので、最前列で撮影できた。しかし、私の薄型デジカメを見て、周りのカメラマンが冷たい視線を注いでいた。そういうことはかまわず、ひたすら取りまくった。
秋田さんの原案は、大阪が舞台で、有名な幕間芸人についてのストーリーだったそうだが、佐々部監督は、それを監督の地元の下関に移して、そこに在日問題と新人記者の話を絡めたそうだ。幕間芸人にあこがれたOLが奥貫薫さんで、やがて結婚して、女の子をもうけた。しかし、映画の斜陽に相まって、妻も急死し、女の子とを残して幕間芸人役の藤井隆が故郷を去っていく。その足跡をたどって、済州島に行った新人記者が父親と娘を結びつける、というストーリーである。
いにしえの映画館が出てきた最初の場面からもう涙腺が活発に活動した。『ニュー・シネマ・パラダイス』の日本版ですから、これだけで弱い。しかも、幕間芸人が映画の浮沈と共に、登場し、退場していくところがさらに泣かせる。
私の思秋期には、既に歌謡曲や大衆演劇よりも、ロードムービーやロックにあこがれたので、この映画に出てくる歌謡曲は半分懐メロのように聞いていたが、だからこそ情感を誘うのだろう。
映画終了後に、秋田さんや監督、俳優さんのインタビューを取りたいと思ったが、上映途中で別の場所に行っておられるとのことで、残念ながら音声は取れなかった。
代わりに、舞台挨拶の写真(http://www.kyoto-seika.ac.jp/tsutsui/friend/akita/index.html)と原案者の秋田さんの思いを以下に転載する。
25年も前になるが、シナリオ修行していた時代、「幻のオルガニスト」というストーリーを書いたことがある。若かりし頃の佐々部監督にこれを話したのだが、彼はその物語をずっと覚えていてくれて、昨春、「映画にしたい」という申し出をもらった。原案は私が高校時代、大阪・千日前で目撃した幕間芸人が元になってはいるが、映画のシナリオは佐々部監督のオリジナルである。
この映画には、私たち大人が語るべきことがたくさん込められている。佐々部監督の真骨頂である「家族愛」についてはもちろんだが、「昭和」とは何であったのか、差別や貧困、あるいは映画館という「場」を通して、その街独自の文化を考えるというふうに、ほんの半世紀前の時代を引用しながら、この映画は私たちの昭和生まれの「カーテンコール」を呼び起こす。
私たちは銀幕にあこがれ、夢と希望をもらった昭和の世代である。希望がない時代と言われる平成の今、この映画から私たちは何かたいせつなものを伝えることができるかもしれない。満員の映画館でみんなで育んだ「希望」や「信頼」を、若い人たちへと語り継ぐことが、昭和を生きた私たち大人の責任ではないか、とも思う。
昭和から平成。私たちの時代とじっくり向き合うことのできる映画の誕生を素直に喜びたい。
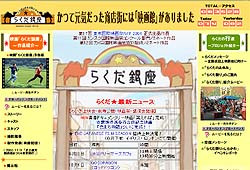
受賞した、と言っても私のことではない。知り合いのことである。
9月熊本の「市民メディア交流集会」で出会った映画監督とプロデューサーが受賞したのである。
http://www.nikkei.co.jp/riaward/jusyou.html#nik3
選考理由は、以下である。
新「西条市」が昨年11月に2市2町合併で誕生、今春、合併記念映画『恋まち物語』を製作した。この製作には少人数の専門家以外に約2700人もの市民が参加・協力した。監督と一緒にロケ地探しをしたり、脚本家の前で自分のまちの魅力についてディスカッションし、脚本作りの素材をそろえたりした。多くの市民が出演し、ボランティアスタッフがロケを支えた。こうした映画製作は合併新市の一体感醸成につながった。今回の製作に当たったFireWorksは、商店街を元気にする娯楽映画「らくだ銀座」製作プロジェクトを2002年から始め、市民参加型の映画製作を続けている。
本人たちがなぜ地域のまちづくりと関わったのかは聞いていないが、まちづくり事業において、コンサートやイベントはよくあるが、映画作りを始める試みはおそらく全国最初だろう。しかも、地域の初心者を参加させた映画作りをするからさすがだ。
11月9日に京都で授賞式がある。その時には、お祝いをしてあげよう。

私自身は、手書き文字が苦手なので習字とは無縁だが、最近習字を習い始めた知り合いから次の話を聞いた。
ある公共施設で開かれる書道教室に習いに行っているが、教師はなんと80歳過ぎの高齢者とのこと。年齢とは裏腹に、かくしゃくとしているし、教え方も非常にうまいそうだ。
どのようにうまいかというと、初心者が書いた作品でもまずいい部分を誉めてから、改善点を指摘する。しかも、必ず見本を教師自ら書いてみせるし、生徒の作品の改善点も朱筆で指摘した後、正しい見本を横に書くとのこと。初心者であっても、数ヶ月通うと少しずつうまくなってくるとやる気が出てくる。すると、生徒の意欲が高まった時を見計らって、教師は本格的に厳しくなってくるそうだ。これで、生徒はさらにうまくなるとのこと。
知り合いは、これまで何人かの教師に習ったそうだが、自ら見本を示しながら、丁寧に教えてくれる書道教師はまれである。しかも、参加費が一回2000円で、来た時だけ払うという格安で来やすい制度は、まさに生徒側から見たら願ってもない条件だし、また優秀な教師の見本そのものである。
経験を積むと、どうしても教師は、発表会や展覧会への出展などのより高度な技を身につけようとする。しかし、習いに来る生徒の多くが「手紙がきれいに書きたい」とか、「文章がきれいに書きたい」という、基礎的な技法を身につけたいという願望と距離ができてしまう。けれども、その書道教師は、手本そのものの字を書くために、生徒の要望にもぴったり合っているそうだ。教師自身も、高齢になっても若い人としっかりと対話できる環境にあることが楽しくてしようがないそうだ。そこには、野心も超えて、世代を超える教師の姿がある。
大学のユニーバーサル化が進行して、学習習慣が身に付いてないにもかかわらず、大学に入学してくる多数の大学生をどう教育するのかは、大学教育の死活問題である。にもかかわらず、初年次教育を担当する教員の多くは、これまで経験してこなかった学生を前にしてなかなか先が見えない状況が続いている。これは私自身にも言える。
高齢の書道教師から学ぶことはあまりにも大きい。

JR車内での仕事ぶり、JR車内アナウンスをダウンロードする。
様々な専門職での現場において、クライアントや客との応対を改善することが望まれている。
しかし、それを改善させる必要性を現場がどこまで感じるかという切実感と、その切実感に応えるトレーナーの人材を確保することが望まれている。しかし、大学内部の人材ではこれに対処できないので、どうしても学外の人材なしでは進まない。
ただ、たとえ外部の優秀な人材であっても、その成果を生かすことができるかどうかは、大学及びそれを支える学内の人材に依存している。大学教育は、非常勤講師なしには成り立たない。外国語、体躯実技、一般教育科目などの基礎教育課程は、履修生が多いので、専任教員だけでは講義を実施することは不可能である。そこで、非常勤講師に依存することになる。こうした大学の財政事情にもかかわらず、多くの非常勤講師の方は熱心に教育されていると思う。けれども、非常勤講師の方に講義をお願いすることを単なる安上がりの便法と考えるとすれば、大学経営としては得策ではない。外部人材をどのように有効に生かすのかが思案のしどころである。
ただ、非常勤講師に依存する講義は、専門科目にもある。大別すると、毎週開講の講義と、一定期間に集中したり、より間隔の空いた(例:月一回)講義との二つ種類ある。前者は近隣の方が多く、後者は他の専門家の方や遠隔地からの講師が該当する。私は以前国立大学に所属していたし、現在の本務校から考えて、いずれの大学でも二種類あるものと思っていた。
しかし、前者はともかく、後者を実施しない大学があることを最近知った。伝統的な大学では、後者は、招聘担当者の既得権として恩師や知り合いを呼ぶことが多く、教育的に生かされているかどうかは必ずしも明確ではない。こうした点は別にしても、非常勤講師の方に講義を担当してもらうとすれば、その講義をカリキュラム全体の中で位置づけることが必要である。
話を戻すが、外部の人材をどのように生かすのかは、受け入れ大学側の体制と熱意が大きい。一方で、幹部の一方的な意向で非常勤講師を決める場合である。多くは、カリキュラム上の必要性よりも、学内行政的な必要性から決定することが多い。逆に、既述のように、受け入れ教員の恣意的な選択である。前者は、教育面が軽視され、後者は受け入れ教員の私物化につながる。両者ともに共通しているのは、教育効果が考慮されていないことである。
教育効果を上げるためには、これら二つの極を排しながら、構想することが重要である。精華大学で非常勤講師の講義(多くは、実技的な講義)の受け入れ担当者になって、従来とは違った前向きのカリキュラムの組み方があることを知った。
つまり、非常勤講師の選定から始まって、講義内容・方式に関して受入教員と事務職員が一緒になって講義を作っていく方法である。講師の選定はもちろん、講義内容・方式について事務職員が関与するのは通常はしない。それは、教員と事務職員との力関係が大きいが、むしろそれ以上に事務職員側が講義内容・方式についてアイデアを提案する能力がないか、関心がないことが大きい。しかし、精華大では、事務職員が積極的に発言し、講師とも直接接触して講義を一緒に作り上げていくことが可能になっている。
もちろん、こうした試みをすべての事務職員が実践できるわけではないので、この体制がどこまで続くのかはわからないが、これが前例となればいいと思う。
ここで、一番最初のテーマに戻る。説明の仕方が、わかりにくい構造になっているのが申し訳ない。
客への応対は、あらゆる職種に不可欠である。ここでは、9月初めに車内で出会った、客にてきぱきと対応されていた客室乗務員兼販売員の方にお話を聞いた。職業意識を持った彼女の対応はインタビューをしていても気持ちがよかった。
列車が終点に近づいて来たので、最後のアナウンスをする前に車掌の制服に着替えた。到着後は、その姿でお客さんにお見送りすることになった。その時には写真が撮れなかったので、販売員の姿を撮らせて頂いた。

昨日、仕事していたら、隣で祇園囃子の調べが聞こえてしまって、最後の部分を見てしまった。テレビ朝日で放映された『祇園囃子』http://www.tv-asahi.co.jp/gion/である。
倉本聡が脚本を書き、石原プロが出演した単発テレビ番組としては、破格の制作費をかけた作品だった。祇園街や友禅職人が舞台なので着物が素晴らしいとか、日本企業や日本社会に対する警告を込めているとかはなんとなくわかったが、地元番組なのでともかく知っている場所や店がどう映っているのかが気になってしまう。何ともミーハー的で情けないが、正直なところだ。
祇園の元お茶屋跡の店は接待用に使うし、百万遍の料亭やプリンスホテルは倉本さんの贔屓だし。
(そういえば、倉本さんは、精華大の学科改組イベントの第一弾として、対談に協力してもらった。対談相手は、倉本さんの東大時代に演劇仲間であった中島貞夫監督であった。親友であっても、初めての対談とのこと。僭越ながら私が司会をさせていただいた。そのときにも料亭の主人も参加されておられた。)
舘ひろしが住んでいる高野川沿いのマンションは屋内を見たことがあるし、渡哲也と対面する大原の料亭はここしかないとのこと。
いずれも直近であるか、所在がわかり、後々いつでも追体験できる場所である。
ドラマ自体は、家紋がヒントになって話が展開していくという倉本さんらしい筋運びである。また、祇園祭の風景をあえて見せないで、音で感じさせるのも、余韻を高めるのに効果的だ。祇園祭は、鉾の祭りではなく、お囃子の音の祭りであったのだ。
暑さも過ぎたこの頃になって、あの暑い盛りに必ずやって来る気持ちの高揚は、いくつになっても忘れることができない。